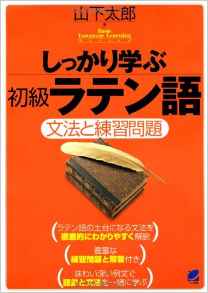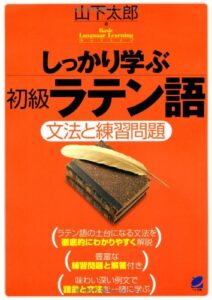不定法
不定法は、現在、未来、完了の3つの時称で現れます。それぞれに能動態と受動態があります。つまり全部で6つの形があります。amōを例に取ると、それぞれ次のような形になります。
| 能動態 | 受動態 | |
| 現在 | amāre | amārī |
| 完了 | amāvisse | amātus,-a,-um esse |
| 未来 | amātūrus,-a,-um esse | amātum īrī |
完了の能動態は、完了幹+isse(~したこと)、完了の受動態は、完了分詞+esse(~されたこと)です。未来の能動態は、未来分詞+esse(~するだろうこと)、未来の受動態は、目的分詞(スピーヌム)+īrī(~されるだろうこと)です。
形式受動態動詞の不定法は能動態の形を持ちません(受動態の3つの時称のみ)。opīnor,-ārī(推測する)を例に取ると、不定法の現在はopīnārī(推測すること)、完了はopīnātus esse(推測したこと)、未来はopīnātūrus esse(推測するだろうこと)となります。未来の形は、受動態のopīnātum īrīの形でなく、能動態のopīnātūrus esse になる点が注意すべきポイントです。
時称に関しては、主文の動詞と比べて「同時」なら現在時称、「以前」なら完了時称、「以後」なら未来時称が使われます。
不定法の基本的用法
ラテン語の不定法は、英語のto不定詞と同じく名詞として使われます。文の主語にも補語にも、目的語にもなります。その場合、中性単数の名詞扱いされます。
Vidēre est crēdere.
見ることは信じることである。
不定法vidēreが主語、crēdereが補語になっています。
Errāre hūmānum est.
間違うことは人間らしい。
主語は不定法errāreで、補語は形容詞hūmānumです。これは第1・第2変化形容詞hūmānus,-a,-umの中性・単数・主格です。つまり、不定法は中性単数の名詞扱いすることが確認できます。
不定法・能動態・現在
ラテン語の不定法・能動態・現在はきわめて重要な形を示しています。この形を見れば動詞の活用の型がわかるからです。amō(愛する)を例にとると、その不定法・能動態・現在は amāre(アマーレ)です。この形は辞書を引くと見出しの右横に書いてあります。たとえば、amō,-āreといった具合にです。辞書を引いたとき、必ずこの形に注意する癖をつけてください。
第1変化動詞: amō,-āre
第2変化動詞: videō,-ēre
第3変化動詞: agō,-ere
第3変化B動詞: capiō,-ere
第4変化動詞: auidō,-īre
初心者の人は、ハイフンで示されても困るかもしれません。amō,-āreはハイフンを使わずに書くと、amō,amāreです。同様に、moneō,monēre、agō,agere、audiō,audīreです。
ハイフンを用いてそれぞれの動詞の語尾を強調しています。この語尾の形でそれぞれの動詞の型が識別できます。

不定法・能動態・現在の例文
それぞれの例文の語彙と文法の説明はリンク先にあります。
Errāre hūmānum est.
過つは人の常。
Incipere multō est quam impetrāre facilius.
始めることは達成することよりはるかに容易である。(プラウトゥス)
Miserīs succurrere discō.
私は惨めな人たちを助けることを学んでいます。(ウェルギリウス)
Quī potest esse vīta vītālis?
どうして人生は生きるに値するものでありえようか。(キケロー)
Vīvere est cōgitāre.
生きることは考えることである。(キケロー)
Licet tibi lacrimāe.
あなたは泣いてもよい。
Imperāre sibi maximum imperium est.
自分を支配することが最大の支配である。(セネカ)
不定法・受動態・現在
不定法の受動態・現在は現在幹に-rīをつけて作ります。ただし、第3変化と第3変化Bは、現在幹から幹末母音eを取り-īをつけます。
第1変化動詞: amārī
第2変化動詞: monērī
第3変化動詞: agī
第3変化B動詞: capī
第4変化動詞: auīrī
不定法・受動態・現在の例文
Sī vīs amārī, amā.
愛されたいなら、愛しなさい。
Fās est et ab hoste docērī.
敵からも教わる(学ぶ)ことは正しい。
Flectī nōn potest, frangī potest.
曲げられることはできないが、壊されることはできる。(セネカ)
不定法・能動態・完了
完了の能動態は、完了幹+isseで表します。「~したこと」と訳せます。amōを例に取ると、不定法・能動態・現在amāreは「愛すること」、不定法・能動態・完了のamāvisseは「愛したこと」となります。
第1変化動詞 amō > amāvisse
第2変化動詞 moneō > monuisse
第3変化動詞 agō > ēgisse
第4変化動詞 audiō > audīvisse
不定法・能動態・完了の例文
In magnīs et voluisse sat est.
偉大なことにおいては志しただけでも十分だ。
Virtūs est vitium fugere et sapientia prīma stultitiā caruisse.
徳は悪徳をさけること。知恵のはじめは愚をもたぬこと。
Cum rērum nātūrā dēlīberā: illa dicet tibi et diem fēcisse sē et noctem.
事物の本性と相談せよ。それ(自然)はあなたに言うだろう、自分は昼も夜も作った、と。



不定法・受動態・完了
完了分詞+esseで表します。少し難しいですが、次の例文をご覧ください(キケロー、『ピリッピカ』1.35より)。
Quārē flecte tē, quaesō, et māiōrēs tuōs respice atque ita gubernā rem pūblicam, ut nātum esse tē cīvēs tuī gaudeant, sine quō nec beātus nec clārus nec tūtus quisquam esse omnīno potest.
太字の部分が「不定法・受動態・完了」です。この一文(長いですが)の語彙と文法はリンク先で説明していますので、詳しくはそちらをご覧ください。全体の逐語訳は次のようになります。
<逐語訳>
それゆえ(Quārē)、君自身を(tē)変えよ(flecte)、お願いだ(quaesō)、そして(et)君の(tuōs)先祖を(māiōrēs)振り返れ(respice)、そして(atque)次のように(ita)国家を(rem pūblicam)導け(gubernā)、すなわち、君が(tē)生まれたことを(nātum esse)君の(tuī)市民達が(cīvēs)喜ぶ(gaudeant)ように(ut)、そのこと(quō)なしに(sine)誰も(quisquam)幸せ(beātus)であることも(esse)高名(clārus)であることも(<esse>)安全(tūtus)であることも(<esse>)まったく(omnīnō)でき(potest)ない(nec…nec…nec)のだ。
不定法・能動態・未来
未来分詞はesse(sumの不定法・能動態・現在)とともに、不定法・能動態・未来を作ります。esseが省略されることもあるので注意が必要です。
不定法・能動態・未来の例文
Crās tē victūrum, crās dīcis, Postume, semper.
ポストゥムスよ、明日自分は生きるだろう、明日になれば、といつも君はいう。
<逐語訳>
明日(Crās)おまえは(tē)生きるだろうことを(uictūtum
不定法・受動態・未来
完了分詞、中性・単数・対格形(=スピーヌムと呼ばれる)+īrī で表します。
不定法の用法
主な用法を紹介します。ラテン語では「対格不定法」が頻出します。



対格不定法
Eās rēs jactārī nōlēbat. Caes.B.G.1.18
彼は、それらの問題が議論されることを望まなかった。
(eās<is [指示代名詞] rēs,-eī f. 問題 jactō,-āre 議論する nōlō,nolle <不定法>を望まない)
この例文で不定法(jactārī)は受動態になりますが、構文自体は対格不定法です。つまり、「AがBされることを望まなかった(nōlēbat)」という構文において、A(eās rēs)が対格になり、B(jactārī)が不定法の受動態になります。
Intellegō tē sapere.
私は君が賢明であると理解している。
「AがBであることを理解する(intellegō)」という構文です。この時、主動詞(intellegō)の主語(ego)と、不定法の意味上の主語(上の例ではtē)が異なるため、後者を対格にします。このtēという対格が不定法sapere(賢明であること)の意味上の主語になっています。
Sī vīs mē flēre, dolendum est prīmum ipsī tibi.
「もし(Sī)私が(mē)泣くことを(flēre)君が望む(vīs)なら、まず(prīmum)君(tibi)自身によって(ipsī)悲しむことがなされるべき(dolendum)である(est)」と言うのが直訳です。
contemnī sē putant, despicī, inlūdī. (Cic.Sen.65)
contemnī: contemnō,-ere(軽蔑する)の不定法・受動態・現在。
sē: 3人称の再帰代名詞suī(自分)の男性・複数・対格。「老人」を指す。
putant: putō,-āre(考える)の直説法・能動態・現在、3人称複数。
despicī: despiciō,-ere(見下す)の不定法・受動態・現在。
inlūdī=illūdī: illūdō,-ere(笑う)の不定法・受動態・現在。
「彼らは自分が(sē)軽蔑され、見下され、笑われていると考える」(中務訳)。
「対格不定法」については、「対格のさまざまな用法」にて詳しく説明しています。
歴史的不定法
不定法が直説法・能動態・未完了過去、または完了の代わりとして用いられることがあります。
Tum Catilīna pollicērī novās tabulās. Sall.Cat.21
その時カティリーナは借金の帳消しを約束した。
pollicērīは形式受動態動詞polliceorの不定法ですが、直説法・完了(pollicitus est)の代わりとして使われています。
練習問題(和訳)
次のラテン語の和訳に挑戦してみましょう。カエサルの『ガリア戦記』に出てくる一文です。「歴史的不定法」が使われています。
Interim cotīdiē Caesar Haeduōs frūmentum, quod essent pūblicē pollicitī, flāgitāre. Caes.B.G.1.16
<語彙と文法>
Interim: その間
cotīdiē: 毎日
Caesar: Caesar,-aris m.(カエサル)の単数・主格。
Haeduōs: Haeduī,-ōrum m.pl.(ハエドゥイー族)の対格。
frūmentum: frūmentum,-ī n.(穀物)の単数・対格。
quod: 関係代名詞quī,quae,quodの中性・単数・対格。先行詞はfrūmentum。
essent: 不規則動詞sum,esseの接続法・未完了過去、3人称複数。pollicitīとともに、形式受動態動詞polliceorの接続法・過去完了、3人称複数を作る。
pūblicē: 「公に」。essent…pollicitīにかかる。
pollicitī: 形式受動態動詞polliceor,-ērī(約束する)の完了分詞、男性・複数・主格。
flāgitāre: flāgitō,-āre(しつこく要求する)の不定法・能動態・現在。「歴史的不定法」。flagitābatの代用。
<逐語訳>
その間(Interim)、カエサルは(Caesar)毎日(cotīdiē)ハエドゥイー族に(Haeduōs)彼らが公に(pūblicē)約束していた(essent…pollicitī)ところの(quod)穀物を(frūmentum)しつこく要求した(flāgitāre)。