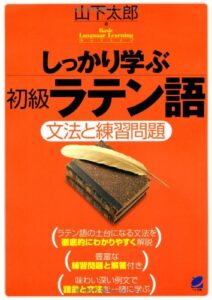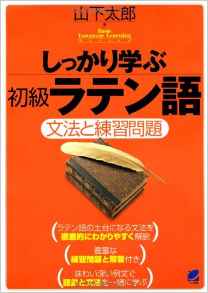形式受動態動詞
英語の文法用語では deponent verbと呼ばれます。日本語訳は「形式所相動詞」、「能動欠如動詞」、「形式受動相動詞」、「異態動詞」などいくつかの呼び方がありますが、本書では「形式受動態動詞」と呼ぶことにします(授業等では発音しやすいので単に「デポーネント」と呼ぶことが多いです)。
形式受動態動詞について
ラテン語の動詞の中には、形は受動で意味は能動というものがあります。絶対数は少ないのですが、どれも頻出語なので注意が必要です。
| 不定法・現在 | 不定法・完了 | 意味 | ||
| 1. | opīnor | opīnārī | opīnātus sum | 推測する |
| 2. | vereor | verērī | veritus sum | 恐れる |
| 3. | loquor | loquī | locūtus sum | 語る |
| 3B. | morior | morī | mortuus sum | 死ぬ |
| 4. | orior | orīrī | ortus sum | 昇る |
活用の種類は不定法・現在の形で区別します。第一変化は -ārī 、第二変化は -ērī、第三変化は -ī 、第四変化は -īrī で終わります。辞書を引くと一般的な動詞と同じく、それぞれの不定法の形が記されています。
形式受動態動詞の例文
Mīrantur dōna Aenēae. (Verg.Aen.1.709)
彼らはアエネーアースの贈り物に驚く。
mīranturはmīror,-ārī(驚く)の直説法・現在、3人称複数です。
Nīl admīrārī.
何にも驚かないこと。
admīrārīはadmīror,-ārī(驚く)の不定法・現在です。
Nescit vox missa revertī.
放たれた言葉は戻ることを知らない。
revertīはrevertor,-vertī(戻る)の不定法・現在です。
Quī sapienter vīxerit aequō animō moriētur.
賢明に生きた人は平静な心で死ぬだろう。
形式受動態動詞の活用は、一般的な動詞の受動態と同じです。この例文でmoriēturはmorior(死ぬ)の受動態・未来の形と一致します(3人称単数)。
Cor ad cor loquitur.
心が心に語りかける。
loquiturはloquor,-ī (語る)の直説法・現在、3人称単数です。
Spem metus sequitur. Sen.Ep.1.5.7
恐怖が希望の後を追う。
sequiturはsequor,-ī (後を追う)の直説法・現在、3人称単数です。
Dum loquor, hōra fugit. Ov.Am.1.11.15
私がおしゃべりする間、時は逃げる。
loquorはloquorの直説法・現在、1人称単数です。
Rēs loquitur ipsa. Cic.Mil.20.53
事実そのものが語る。
loquiturはloquor,-quī(語る)の直説法・現在、3人称単数です。
Indignor quandōque bonus dormītat Homērus. Hor.A.P.359
立派なホメールスが居眠りするたび私は憤慨する。
Indignorはindignor,-ārī(憤慨する)の直説法・現在、1人称単数です。
Fugācēs lābuntur annī. Hor.Carm.2.14.1
逃げ足の早い歳月が過ぎていく(歳月は逃げ足早く過ぎていく)。
lābunturはlābor,-bī(流れる、過ぎる)の直説法・現在、3人称複数です。
Glōria virtūtem tamquam umbra sequitur. Cic.Tusc.1.109
栄光は美徳に影のように付き従う。
sequiturはsequor,-quī(従う)の直説法・現在、3人称単数です。
Et scelerātīs sōl orītur. Sen.Ben.4.26.1
極悪人のためにも太陽は昇る。
orīturはorior,-īrī(昇る)の直説法・現在、3人称単数です。
Cūrae levēs loquuntur, ingentēs stupent. Sen.Ph.607
軽い不安は語り、大きな不安は沈黙する。
loquunturはloquor,-quī(語る)の直説法・現在、3人称複数です。
Nītimur in vetitum semper cupimusque negāta. Ov.Am.3.4.17
我々は常に禁じられたものを得ようと努め、否定されたものを欲する。
nītimurはnītor,-tī(in + <対格>を得ようと努める)の直説法・現在、1人称複数です。
Male parta male dīlābuntur. 不正な方法で入手したものは悪い仕方で手元から消えていく。
dīlābunturは形式受動態動詞dīlābor,-ī(消える)の直説法・未来、3人称複数です。
Hōrae quidem cēdunt et diēs et mensēs et annī; nec praeteritum tempus umquam revertitur; nec quid sequātur scīrī potest. Cic.Sen.69
実際時間や日、月や年は進みゆく。過ぎ去った時は決して戻らない。何が後に続くかは知られることができない(を知ることはできない)。
sequāturはsequor,-quī(続く)の接続法・現在、3人称単数です。quidで導かれる間接疑問文中の動詞なので接続法になります。
Quem dī dīligunt adulescens moritur.
神々が愛する者は若死にする。
moriturはmorior,morī(死ぬ)の直説法・現在、3人称単数です。
半形式受動態動詞
若干の動詞は、現在、未完了過去、未来の時称では普通の動詞のように活用し、完了系時称(完了、未来完了、過去完了)で形式受動態動詞のように活用するものがあります。
| 直説法・能動態・現在 | 不定法・能動態・現在 | 直説法・受動態・完了 | 意味 |
| audeō | audēre | ausus sum | あえて行う |
| fīdō | fīdere | fīsus sum | 信頼する |
| gaudeō | gaudēre | gāvīsus sum | 喜ぶ |
| soleō | solēre | solitus sum | 習慣としている |
audeō(あえて行う)を例にとると、audēreは「あえて行うこと」を意味し、ausus sumは一見受動態として訳すかに見えて「(私は)あえて~行った」と訳す点に注意が必要です。
同様に、fīsus sumは「私は信頼した」、gāvīsus sumは「私は喜んだ」、solitus sumは「私は習慣としていた」となります。
半形式受動態動詞の例文
hīc prīmum Aenēās spērāre salūtem ausus,… Verg.Aen.1.451-452
ここではじめてアエネーアースは勇気をふるって救済の希望を持ち
(hīc ここで prīmum はじめて Aenēās,-ae m. アエネーアース spērō,-āre 希望する salūs,-ūtis f. 救済 ausus<audeō 勇気を出して~する)
aususはaudeōの完了分詞、男性・単数・主格でAenēāsと性・数・格が一致します。この形は本来受動の意味を持つはずですが、「audeōは完了系の時称で形式受動態動詞として使われる」ということに注意します。この例文を見ると、確かにspērāreを目的語に取る他動詞として使われていることが確認できます。
形式受動態動詞の現在分詞と未来分詞
現在分詞と未来分詞は能動の意味を持ちます。現在分詞は、一般動詞の現在分詞と同じく第一変化動詞には-ansをつけ、それ以外には-ensをつけます。
形式受動態動詞の現在分詞と未来分詞の例文
Illa manū moriens tēlum trahit. Verg.Aen.11.816
彼女は死が迫りながらも手で槍を抜く。
(manus,-ūs 手 f. morior,-ī 死ぬ tēlum,-ī n. 槍 trahō,-ere 抜く)
moriensは形式受動態動詞morior,morī(死ぬ)の現在分詞でillaと性・数・格が一致します。指示代名詞illaは、原文を参照すると女戦士カミラを指すことがわかります(引用個所は彼女の死を描く場面です)。moriensは「死にながら」という意味ですが、日本語らしくするには「息も絶え絶えになりながら」等、意訳の工夫が必要です。
Avē imperātor, moritūrī tē salūtant. Suet.DivusCalud.21
さらば将軍よ、死にゆく者たちがあなたに(最後の)挨拶をする。
(avē さようなら imperātor,-ōris m. 将軍 morior,-ī,mortuus sum 死ぬ salūtō,-āre 挨拶する)
moritūrīはmorior,morī(死ぬ)の未来分詞moritūrus,-a,-um(死のうとしている状態の)の男性・複数・主格です(moritūrusの形は若干不規則です)。
形式受動態動詞の完了分詞
「~しながら」の意味を持ちます。
Ipse pater dextram Anchīsēs haud multa morātus dat juvenī. Verg.Aen.3.610-611
父アンキーセース自身は、少しためらってから右手を若者に与える。
(dextra,-ae f. 右手 Anchīsēs,-ae m. アンキーセース、アエネーアースの父 haud multa 少し moror,-ārī,morātus sum ためらう dō,-are 与える juvenis,-is c. 若者)
morātusは形式受動態動詞moror,-ārī(ためらう)の完了分詞で、主語Anchīsēsと性・数・格が一致します。「ためらいながら」と訳します。形式受動態動詞は完了分詞で能動の意味を持ちます。
fīsus cuncta sibi cessūra perīcula Caesar,… Lucan.5.577
カエサルはあらゆる危険は自分に屈服すると信じつつ、
fīsusはCaesarと性・数・格が一致します。fīsusはfīdō,-ere(信じる)の完了分詞でありながら能動の意味を表します。fīdōは半形式受動態動詞の一つで、完了分詞を含む完了系時称で形式受動態動詞になります。この例文において、「信じている内容」はfīsusと比較して「以後」の事柄に相当するため、不定法・能動態・未来が使われています(cessūra esseとなるところ、esseは省略されています)。また、この不定法の意味上の主語に当たるcuncta perīculaは対格(中性・複数)です(「対格不定法」)。
形式受動態動詞の動名詞
一般動詞の動名詞と同じく、現在幹に-ndumをつけて作ります。
1 opīnor: opīnandum(推測すること)
2 vereor: verendum(恐れること)
3 loquor: loquendum(語ること)
3B morior: moriendum(死ぬこと)
4 orior: oriendum(昇ること)
形式受動態動詞の動名詞の例文
Aegrescit medendō. Verg.Aen.12.46
彼はなだめることで感情が激する。
(aegrescō,-ere 悪化する、感情が激する medeor,-ērī 治療する、なだめる)
medendōは形式受動態動詞medeor,-ērī の動名詞medendumの奪格です。主語は、原文ではアエネーアースの宿敵トゥルヌスですが、この表現はオリジナルの文脈から離れ、「治療によって、かえって病状が悪化する」という意味の格言として知られます。
形式受動態動詞の動形容詞
Omnibus hominibus moriendum est.
すべての人間は死すべき存在である。
これは、動形容詞の非人称表現の例文になります。moriendum は形式受動態動詞morior,morī(死ぬ)の動形容詞で、行為者「すべての人間」(omnibus hominibus)は与格で表されています(「行為者の与格」)。
形式受動態動詞の目的語
Dī mē tuentur.
神々は私を見守り給う。
(deus,-ī m. 神 mē<ego [人称代名詞] tueor,-ērī 見守る)
tuentur(形式受動態動詞tueor,-ērī の直説法・現在、3人称複数)は、mē(1人称単数の人称代名詞egoの対格)を目的語に取ります。
一方、属格や奪格の目的語を取る形式受動態動詞もあります。ただし、属格支配の動詞であっても、辞書を引くと対格や奪格支配の例が見つかることもあります(主として時代や作家の好みによって幅が出ます)。実際に原文を読む場合は辞書で一つ一つ用例を確認することが大切です。
属格を目的語に取る例
oblīviscor(忘れる)やreminiscor(思い出す)などは属格を目的語に取ります。
Ita prorsum oblītus sum meī. Ter.Eun.2.3.15
こうして私は自分のことをすっかり忘れてしまった。
(ita このように prorsum すっかり oblītus sum<oblīviscor 忘れる meī:ego の属格)
oblītus sumは形式受動態動詞oblīviscor,-scī(忘れる)の直説法・完了、1人称単数です。
Aliī reminiscēbantur veteris fāmae. Nep.Phoc.4
昔の名声を思い出す者たちもいた。
(aliī<alius他の [代名詞的形容詞] reminiscēbantur<reminiscor 思い出す vetus,-eris 昔の fāma,-ae f. 名声)
reminiscēbanturは形式受動態動詞reminiscor,-scī(思い出す)の直説法・未完了過去、3人称複数です。
奪格を目的語に取る例
fruor(享受する)、potior(手に入れる)、ūtor(用いる)などは奪格を目的語に取ります。
Beātī aevō sempiternō fruuntur. Cic.Rep.6.13
幸福な者たちは永遠の命を享受する。
(beātus,-a,-um 幸福な aevus,-ī m. 生涯、寿命 sempiternus,-a,-um 永遠の fruuntur<fruor,-ī 享受する)
fruunturは形式受動態動詞fruor,-ī(享受する)の直説法・現在、3人称複数です。この文ではaevōを目的語にとっています。
urbe potīrī
都市を手に入れること
(urbs,-is f. 都市 potior,-īrī 手に入れる)
potīrīは形式受動態動詞potior,-īrī(手に入れる)の不定法・現在です。urbeを目的語にとっています。
Dē rēbus ipsīs ūtere tuō jūdiciō. Cic.Off.1.2
事柄そのものについては自分の判断を用いるがよい。
(dē <奪格>について rēs,-eī f. 事柄 jūdicium,-iī n. 判断)
ūtereは形式受動態動詞ūtor,ūtī(用いる)の命令法・現在、2人称単数です。jūdiciōを目的語にとっています。
形式受動態動詞の命令法
形は受動態の命令法と同じです。
ignem gladiō scrūtāre.
火を剣でかき立てよ。
(scrūtor,-ārī 詮索する、つつく、かき立てる)
Vērē ac līberē loquere.
ありのまま自由に語れ。
(vērē 正しく、ありのままに ac=atque そして līberē 自由に loquor,-quī 語る)
loquereは形式受動態動詞loquor,-quī(話す、語る)の命令法・現在、2人称単数です。
Sequere nātūram.
自然に従え。
(sequor,-quī 従う nātūra,-ae f. 自然)
Sequereは形式受動態動詞sequor,-quī(従う)の命令法・現在、2人称単数です。
Turne, in tē suprēma salūs, miserēre tuōrum. Verg.Aen.12.653
トゥルヌスよ、おまえに最後の希望がかかっている。仲間を憐れむがよい。
(Turne<Turnus,-ī m. トゥルヌス in <奪格>に suprēmus,-a,-um 最後の salūs,-ūtis f. 安全 misereor,-ērī <属格>を憐れむ)
miserēreは形式受動態動詞misereor,-ērī(憐れむ)の命令法・現在、2人称単数です。
形式受動態動詞の不定法
Mementō morī.
死ぬことを忘れるな。
morīは形式受動態動詞morior,morī(死ぬ)の不定法・現在です。
Dulce et decōrum est prō patriā morī. Hor.Carm.3.2.13
祖国のために死ぬことは快く、美しい。
morīは形式受動態動詞morior,morī(死ぬ)の不定法・現在です。
Scīre loquī decus est; decus est et scīre tacēre.
語ることを知ることは名誉である。沈黙することを知ることもまた名誉である。
loquīは形式受動態動詞loquor,-quī(語る)の不定法・現在です。