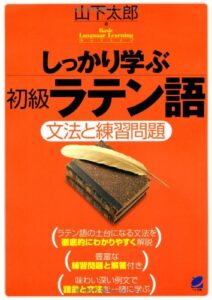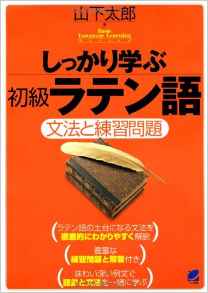関係代名詞についての把握の仕方は、英語と同じで大丈夫です。英語のwho、whose、whomと同じく、ラテン語の関係代名詞の格は、先行詞の従属文での役割に応じて決定されます。英語と違うのは、先行詞と性と数を一致させる点です。
関係代名詞の変化
関係代名詞 quī「ところの人(もの)」
| 男性 | 女性 | 中性 | |
| 単数・主格 | quī | quae | quod |
| 属格 | cūjus | cūjus | cūjus |
| 与格 | cuī | cuī | cuī |
| 対格 | quem | quam | quod |
| 奪格 | quō | quā | quō |
| 複数・主格 | quī | quae | quae |
| 属格 | quōrum | quārum | quōrum |
| 与格 | quibus | quibus | quibus |
| 対格 | quōs | quās | quae |
| 奪格 | quibus | quibus | quibus |
※複数・与格と奪格はquibusの代わりにquīsが使われる場合があります。

この表は「疑問形容詞」の表と同じです。
関係代名詞の例文
主格の例
先行詞を伴う例
Nēmō līber est quī corporī servit. Sen.Ep.92.33
肉体に従う者は誰も自由ではない。
先行詞はNēmō(英語のnobody)です。quīはservitの主語です。
Deus ille fuit quī princeps vītae ratiōnem invēnit. Lucr.5.8-9
人生の原理を最初に発見した彼こそは神であった。
先行詞はilleです。quīはinvēnitの主語です。
Nōn omne quod nitet aurum est.
輝くものすべてが黄金とは限らない。
先行詞はomneです。quodはestの主語です。
先行詞が省かれる例
先行詞が省略される例は数多くみられます。
Deum colit quī nōvit. Sen.Ep.95.47
神を知る者は神を敬う。
先行詞illeが省かれています。quīはnōvitの主語です。
Bis vincit, qui se vincit in victoria.
勝利において己に勝つ者は二度勝つ。
先行詞illeが省かれています。quīはvincitの主語です。
Dīmidium factī quī coepit habet.
(事を)始めた人は業績の半分を持つ(終えたことになる)。
先行詞はilleが省かれています。quīはhabetの主語です。
Crās amet, quī numquam amāvit; quīque amāvit, crās amet.
愛したことのない者は明日愛すがよい。愛したことのある者は明日も愛すがよい。
先行詞illeが省かれています。二つのquīはいずれもamāvitの主語です(一つ目のamāvitはnumquamで否定されています)。
属格の例
Ō fortūnātī, quōrum jam moenia surgunt! Verg.Aen.1.437
おお、その者の城壁がすでにそびえているところの幸福な者たちよ(直訳)
quōrumの先行詞はfortūnātīです。
与格の例
Numquam est ille miser cuī facile est morī. Sen.Herc.Oet.111
死ぬことがたやすい者は惨めでは決してない。
cuīの先行詞はilleです。cuīは「判断者の与格」です。
対格の例
Age quod agis.
あなたのしていることをせよ。
quodの先行詞idは省略されています。quodはagisの目的語です。
Hominēs id quod volunt crēdunt.
人間は(信じたいと)望むことを信じる。
quodの先行詞はidです。quodはvoluntの次に省略された不定法crēdereの目的語です。
Levis est Fortūna: cito reposcit quod dedit.
運命の女神は軽薄である。与えたものをすぐに返すよう求めるから。
quodの先行詞idは省かれています。quodはdeditの目的語です。
奪格の例
Cārum ipsum verbum est amōris, ex quō amīcitiae nōmen est ductum. Cic.N.D.1.12
愛(アモル)という言葉自体魅惑的であり、この言葉から友愛(アミーキティア)の名称も生まれたのである。
Cārum は第1・第2変化形容詞cārus,-a,-um(魅惑的な)の中性・単数・主格。
ipsum は強意形容詞ipse,-a,-um(自ら、自身)の中性・単数・主格。verbumにかかります。「言葉自身」。
verbum はverbum,-ī n.(言葉)の単数・主格です。
est は不規則動詞sum,esse(である)の直説法・現在、3人称単数です。
amōris はamor,-ōris m.(愛)の単数・属格です。verbumにかかります。「説明の属格」です。
ex は「<奪格>から」を意味する前置詞です。
quō は関係代名詞quī,quae,quodの中性・単数・奪格です。verbumを先行詞とします。非制限用法とみなします(quōを指示代名詞eō<is,ea,idの中性・単数・奪格>の代用とみなします)。
amīcitiae はamīcitia,-ae f.(友情)の単数・属格です。nōmenにかかります。「説明の属格」です。
nōmen はnōmen,-minis n.(名称)の単数・主格です。
est は不規則動詞sum,esseの直説法・現在、3人称単数です。
ductum はdūcō,-ere(導く)の完了分詞、中性・単数・主格です。est ductumの形は、dūcōの直説法・受動態・完了、3人称単数です。
「愛という(amōris)言葉(verbum)自体(ipsum)魅惑的(Cārum)であり(est)、これ(=この言葉)(quō)から友愛の(amīcitiae)名称が(nōmen)導かれた(est ductum)」と訳せます。
先行詞が関係代名詞の後に来る例
Quis est, quī complet aurēs, tantus et tam dulcis sonus? Cic.Rep.6.18
耳を満たす、これほど大きく、これほど妙なる調べは一体何なのか。
quīの先行詞は文末のsonusです。
代名詞としての用例
実際のラテン語を読むと、この用例が実は一番多いと感じます。
Quae dum in Asiā geruntur,… Nep.Han.12
またこれらが小アジアでなされていた間、
quaeは関係代名詞の中性・複数・主格(quodの複数・主格)ですが、Et haec(指示代名詞hicの中性・複数・主格)の代わりとして用いられています。
Q.E.D. 証明終了
Quod erat dēmonstrandum.の略です。QuodはEt id(そしてそれは)の代わりです。
関係形容詞
関係代名詞は、そのままの形で関係形容詞としても用いられます。
Quam ob causam summus ille caelī stellifer cursus,… Cic.Rep..6.18
またこの理由により、星を運ぶ最も高いあの天の軌道は、・・・
(ob <対格>のために causa,-ae f. 理由 summus,-a,-um 最も高い ille あの[指示形容詞] caelum,-ī n. 天 stellifer,-fera,-ferum 星を運ぶ cursus,-ūs m. 軌道)
quamはcausamにかかる形容詞としての働きをしています。したがって、ともに性・数・格が一致します(女性・単数・対格)。
不定関係代名詞
次の(1)と(2)は、英語のwhoeverやwhateverに相当する不定関係代名詞です。
(1)quisquis(m.f.)、quidquid(またはquicquid)(n.)
(2)quīcumque(m.)、quaecumque(f.)、quodcumque(n.)
どちらも「~する人(物)は誰(何)でも」を意味します。(1)は疑問代名詞を重ねた形で(quemquem、quōquōなど)、代名詞的に用います。(2)は疑問形容詞の語尾に-cumqueをつけたもので、代名詞的にも形容詞的にも用います。
Quidquid praecipiēs, estō brevis. Hor.A.P.335
あなたが何を教えるにせよ、短くあれ。
Quidquidは上の(1)の例です。
Quaecumque est fortūna, mea est. Verg.Aen.12.694
運命がどのようなものであれ、それは私のものだ。
Quaecumqueは上の(2)の例です。
関係副詞
英語のwhereに相当する語として、ラテン語にはubiやunde、quōやquāといった関係副詞があります。
Fidēs, ut anima, unde abiit, eō numquam redit.
信頼は魂と同じく、立ち去ったところに二度と戻らない。
Ubi amīcī ibīdem sunt opēs. Pl.Truc.885
友のいるところ、そこには富がある。
Ubicumque homō est, ibi beneficiī locus est. Sen.Vit.24.3
人間のいるところはどこであれ、そこには善行の機会がある。