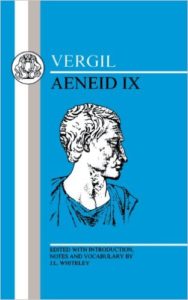ラテン語の属格の用法
属格(ぞっかく)は英語の所有格と基本的に同じです。ただし、英語の所有格以外にも様々な用法があります。主だった用法と訳し方のコツをまとめます。
所有の属格
属格の一番よく見られる用法が「所有の属格」です(英語の所有格のはたらき)。
Māter artium necessitās.(必要は技術の母である)において、どこに属格が使われているでしょうか。語彙は次のとおりです。「māter,-tris f. 母 ars,-tis f. 技術 necessitās,-ātis f. 必要、困窮」。答えはartiumです。arsの変化表のどこにartiumがみつかるか、というと、この単語が第3変化名詞であることを知り、第3変化名詞の表で語尾が-umになる箇所を見ます。答えは、複数・属格です。この文は訳がついているので、主語がnecessitās、補語がMāterとわかります。しかし、SVCの構文において、ラテン語は主語と補語を逆にしても文法的には間違いではありません。「技術の母は『必要』である」としても意味が通るならそれでもよいです。訳文がなくて、一から自分で解釈する場合、artiumを Māterかnecessitāsか、どちらにかければよいか、迷う場合が出てきます。A B Cと3つの単語が並び、真ん中のBが属格で、AとBが名詞の主格の場合、BをAにかけても、Cにかけても、文法的にはどちらも正解です。つまり、artiumをnecessitāsにかけて、「技術の必要は母である」と訳すことも可能です。ただし、意味が不鮮明なのでこれはないと判断します。しかし、その可能性も考慮する必要があります。英語と異なり、語順が自由だからこそ生じる難しさがここにあります。
もう一つ別の例を見ましょう。Ō vītae philosophia dux.(Cic.Tusc.5.5)はどう訳せばよいでしょうか。vītaeが vīta(人生)の単数・属格で、philosophia(哲学)とdux(指導者)が単数・呼格です。「人生の」を「哲学」か「指導者」かどちらにかければよいか、という問題があります。一般的に単語として「近い」ほうにかけると判断するのが普通でしょう。しかし、ラテン語は遠くてもかけることは可能です。「おお(Ō)人生の(vītae)哲学(philosohia)である指導者よ(dux)」と訳すか、「おお(Ō)人生の(vītae)指導者(dux)である哲学よ(philosophia)」と訳すか、どちらかです。正解は後者です。vītaeはphilosophiaをとばし、位置的に「遠い」duxにかかるわけです。
属格の述語的用法
Hominis est errāre.(間違うことは人間の特質である)という例文を見ましょう。語彙は、「homō,-minis c. 人間 errō,-āre 間違う」です。この文を直訳すると、「間違うことは(errāre)人間の(hominis)である(est)」となり、「人間の」の次に「性質」や「特質」といった言葉を補って理解します。hominisが「述語的に」(=文の述語として)使われている例です。
もう一つ例を見ましょう。Pauperis est numerāre pecus.(Ov.Met.13.824)はどう訳せばよいでしょうか。語彙は、「pauper,-eris 貧しい numerō,-āre 数える pecus,-oris n. 家畜」です。文頭のPauperisはpauperの男性・単数・属格です。形容詞ですが、「貧乏人」を意味する名詞として使われています。Pauperis estだけで、「『貧乏人の』(pauperis)である(est)」となります。「貧乏人の性質である」と解釈します。主語は不定法 numerāre(数えること)です。その目的語がpecusです。pecusは中性名詞なので、主格と対格が同じ形です。ここは対格ととります。全体をまとめると、「家畜の数を数えるのは貧乏人の性分である」という訳語が得られます。「貧乏人の」の次に「性格」や「性分」という日本語を足して理解しないといけない点で、難易度の高い例文となります。
Boni est viri etiam in morte nullum fallere.のvirīも「属格の述語的用法」です。bonus,-a,-um(善い)、mors,mortis f.(死)、nullum=nobody、fallō,-ere(欺く)と単語の意味を紹介しますので、どのような意味になるか少し考えてみてください。答えはリンク先で確認できます。
部分の属格
「全体の一部分」を表す表現で、「全体」に当たる語を属格で表します。例文を見ましょう。Hōrum omnium fortissimī sunt Belgae. (Caes.B.G.1.1)は「これらすべての(部族)の中で最も勇猛なのがベルガエ族である。」と訳せます。語彙は「hōrum: hic,haec,hoc(これ、この)の男性・複数・属格 omnium:omnis,-e(すべての)の男性・複数・属格 fortis,-e 強い、勇猛な」です。
主語的属格
名詞+属格をA of Bで表す時、BがAの含意する行為の主語に当たる表現とみなせる場合、この属格を「主語的属格」と呼びます。Amor deī magnus est.(神の愛は大きい。)において、属格はdeī(神の)です。Amor deīを「神の愛」と訳しますが、この「愛」は誰の愛か、誰が愛するのか、と問えば神自身です。属格のdeīはこの主語が誰かを示すので、「主語的属格」とみなします。
目的語的属格
今見たamor deīですが、文脈次第では「目的語的属格」の例ともみなせます。たとえば、「(人間の)神への愛」と解釈できる場合、deīの部分は、(人間が)「愛する」対象を示すので、「目的語的属格」とみなします。基本的に、「~への」、「~に対する」と訳せばよいです。
別の例を見ましょう。lacrimae rērum (Verg.Aen.1.462)はどう訳せばよいでしょうか。語彙は、「lacrima,-ae f. 涙 rēs,-eī f. 人間の営み」です。rērumはrēsの複数・属格でlacrimae(複数・主格)にかかります。このrērumを目的語的属格ととるとき、「人間の営みに対する涙」と訳せます。これを踏まえた上で「人間の営みに流す涙」など意訳することは可能です。
別の例としてmetus hostium(敵への恐怖)を挙げましょう。hostium(hostisの複数・属格)は敵に対して抱く恐怖とみなせば「目的語的属格」ですが、敵が抱く恐怖とみなせば「主語的属格」です。どちらが適切かは文脈によって決定されます。
Cultūra animī philosophia.のanimīも「目的語的属格」です。animīはCultūraにかけ、「精神の耕作は」と訳しますが、これだと何のことかわかりません。「精神を耕すことは」ととらえると意味が通るでしょう。訳は、「精神を耕すことが哲学である」(または、「哲学は精神を耕すこと」)。
性質の属格
例えば日本語で「黒い眼鏡の男」という時、「黒い眼鏡」が「男」を所有しているわけではなく、「男」の特徴や性質を説明しています。これと同じ用法がラテン語の属格に見られます。
例を見ましょう。vir magnae sapientiae(大きな知恵の男)のsapientiae(sapientiaの単数・属格)は、vir(男)の性質を表すので、「性質の属格」と判断できます。語彙のヒントは次のとおりです。「vir,virī m. 男 magnus,-a,-um 大きな sapientia,-ae f. 知恵」。訳例は直訳ですが、これを「大きな知恵を持つ男」と言い換えることもできます。この表現は、実際の文中で次のように使われます。Fortūna adversa virum magnae sapientiae nōn terret.(逆境は大きな知恵を持つ男を脅かさない)。
説明の属格
名詞の意味を説明する働きをする属格があります。これを「説明の属格」と呼びます。praemium vītae aeternae(永遠の命という報酬)というラテン語で、属格のvītaeはpraemiumの内容を説明しています。これを「説明の属格」と呼びます。語彙は「praemium,-iī n. 報酬 vīta,-ae f. 命 aeternus,-a,-um 永遠の」です。
別の例を見ましょう。Quis genus Aeneadum, quis Trōjae nesciat urbem? Verg.Aen.1.565(誰がアエネーアースの一族を、誰がトロイヤの都を知らないだろうか)において、AeneadumとTrōjaeはともに属格ですが、それぞれgenusとurbemの説明をしています。単語の説明は次のとおりです。「quis 誰が genus,-eris n. 一族 Aeneadēs,-ae m. アエネーアースの仲間 Aeneadumは複数・属格形 nesciō,-īre 知らない urbs,urbis f. 都」。
価値の属格
価値や値打ちを表すさい、属格を使うことができます。Is quidem nihilī est quī nihil amat. Pl.Pers.179-180(何も愛さない者は、まったく何の値打ちもない)において、nihilī(単数・属格)は「価値の属格」とみなせます。語彙は、「quidem まったく nihilum,-ī n. 無 nihil 無 amō,-āre 愛する」です。
別の例を見ましょう。In rēbus dubiīs plūrimī est audācia. Syr.298(危機的状況では勇気が最大の価値を持つ)において、plūrimīは「価値の属格」です。語彙は、「rēs,-eī f. 状況 dubius,-a,-um 危機的な plūrimus, -a,-um 最大の、最高の audācia,-ae f. 勇気」です。
目的語の属格
動詞や形容詞の中には属格を目的語に取るものがあります。veteris contumēliae oblīviscī Caes.B.G.1.14(古い侮辱を忘れること)というラテン語で、contumēliaeは単数・属格ですが、不定法oblīviscīがこの「属格」を求めています。語彙は、「vetus,-eris 古い contumēlia,-ae f. 侮辱 oblīviscor,-ī <属格>を忘れる」です。
別の例をあげます。Vīve memor mortis.(死を記憶して生きよ)において、memorは「属格」を記憶するという意味を持ちます。mortisはmorsの単数・属格で、何を記憶しているかの情報を伝えます。
次の例文の属格の使い方にも注意して下さい。Populī Rōmānī est propria lībertās.(自由はローマ国民固有のものである)において、Populīが属格になるのは、propriaがこの形を要求するためです。語彙は、「populus,-ī m. 国民 Rōmānus,-a,-um ローマの proprius,-a,-um <属格>に特有の、固有の lībertās,-ātis f. 自由」です。