
京都INOBUNの壁
Festina lente.は「ゆっくり急げ」を意味するラテン語です。
語彙と文法
「フェスティーナー・レンテー」と読みます。
festīnā はfestīnō,-āre(急ぐ)の命令法・能動態・現在、2人称単数で、「急ぎなさい」を意味します。
不定法の形(-āre)から第1変化動詞とわかります。amō,-āre(愛する)と同じ活用をします。
lentē は「ゆっくりと」を意味する副詞です。
全体で「ゆっくり急げ」という意味になります。
少しニュアンスは異なりますが、「急がば回れ」と意訳することも可能です。
ローマの初代皇帝アウグストゥスの座右の銘であったとローマの歴史家スエートーニウスは伝えています。
アウグストゥスは元のギリシア語σπεύδε βραδέως(スペウデ・ブラデオース)を口にしました。Festīnā lentē.はそのラテン語訳です。
スエトニウスは、アウグストゥスの座右の銘を三つ紹介していますが、その一つ目がこの言葉のギリシア語版、二つ目もギリシア語で「大胆な指揮官より慎重な指揮官がまし」というもの、三つ目はラテン語で、「立派にできたことは十分早くできたこと」。どれも向こう見ずを諌め、慎重さを重んじる言葉と受け取ることができます。
Festina Lenteをめぐって
表題は有名なラテン語の言葉です。日本で最初の西洋古典学者田中秀央先生の座右の銘でした。ケーベル先生から授かった言葉と聞きます。あれもこれも言葉を学ぼうとしてあせっていた田中先生にケーベル先生いわく、「フェスティーナー・レンテー」だぞと。かなり意訳すると「あせるな、じっくりやれ」となるかもしれません。関西弁だと「ぼちぼちいこか」とでも。
日本で西洋古典を学ぶ人は必ずギリシア語、ラテン語をマスターしなければならず、文字通り寝食を忘れて努力しないといけないわけです。その結果、それなりの力がついても、本人としてはまだまだ何も身についていない、と思い、絶望にも近い気持ちが押し寄せるものです。田中先生もそうだったのでしょうか。
田中先生のご自宅は北白川にあり、なんと私の家と通りをひとつ隔てた場所にあります(といっても距離的には少しありますが)。私が生まれた頃、立派な勲章をもって幼稚園の園児たちに見せに来てくださったこともあったそうです(園長であった父から聞きました)。ちょっとこじつけになりますが、今、「北白川でギリシア語、ラテン語を教える私塾を開いている」ことに私はある種のご縁を感じます。
と書いてきて思い出したことがあります。それは、田中先生の作られた辞書に関する学生のレポートのことです(「『初版まへがき』を読んで厳粛な感動に心を打たれました。」という一文を含むもの)。学生と言っても、会社を退職して聴講生をされていた方で、いつも最前列に座って実に熱心に学ばれました。この方とは年賀状のやりとりを続けていましたが、ある年、奥様から訃報を知らされました。
研究社の「羅和辞典」としては旧版になりましたが、今でもこの本を手にするとそうしたことも含め、様々な思い出が去来します。
羅和辞典
田中 秀央

Festina lenteの日本語訳:悠々として急げ
さて、Festina lente.という言葉に話を戻すと、この表現は一般に「急がば回れ」と訳されることが多い印象です。直訳はあくまでも「ゆっくり急げ」です。これを何と訳すと言葉本来の力が引き出せるのか。このことに関して、読者の方から開高健氏の日本語訳を教えていただきました。それは『悠々として急げ』というものです。副詞lenteの訳を直訳の「ゆっくりと」から「悠々として」に変えるだけでこれだけ言葉の表情が変わるのですね。これだとアウグストゥスにもお似合いです。

アウグストゥス
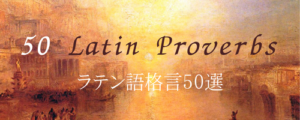

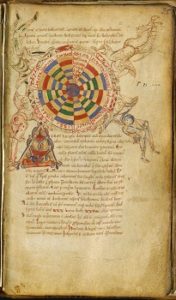


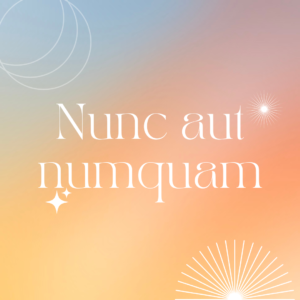

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] マイペースでこつこつ進む。これもFestina lente.(フェスティーナー・レンテー)の一つの解釈です。 […]