
語彙と文法
「アニミース・オピブスクゥェ・パラーティー」と読みます。
animīsはanimus,-ī m.(心)の複数・奪格。「場所の奪格」とみなせます。「心において」。
opibusはops,opis f.(力、能力)の複数・奪格で、animīsと同じく「場所の奪格」です。この語は複数で「資力、財産、兵力、軍勢」を意味します。
-queは「そして」を意味します。Animīsとopibusをつなぎます。
parātīは第1・第2変化形容詞parātus,a,-um(準備のできた)の男性・複数・主格です。
主語として「彼らは」を補って考えます。parātīは文の補語とみなします。
「(彼らは)心(Animīs)と(-que)資材において(opibus)準備のできた状態で(parātī)」というのが直訳です。
元の詩では動詞convēnēre(参集した)にかかる副詞句になっています。
「心と資材の点で準備ができている」と訳して差し支えありません。
言葉の背景
サウス・カロライナ州のモットーとして知られますが、元はウェルギリウスの『アエネーイス』に見られる表現です(Aen.2.799)。モットーの場合、省略された主語は「私たちは」(nōs)ということになるのでしょう。
場面はちょうど第2巻の終わり、主人公が燃え盛るトロイアをあとにし、へスペリア(西の国)を目指して船を出そうとするところです。表題の言葉を含む元の詩を「対訳」の形で引用します。太字の部分が今回ご紹介するラテン語です。
Atque hic ingentem comitum adfluxisse nouorum
inuenio admirans numerum, matresque uirosque,
collectam exsilio pubem, miserabile uulgus.わたしは、その場に新しい顔ぶれの仲間が多数集まっているようすを
目の当たりにし、驚いた。男も女も、
亡命のために結集した若者たちもいた。惨めな群衆ではあった。undique conuenere animis opibusque parati
in quascumque uelim pelago deducere terras. 800
iamque iugis summae surgebat Lucifer Idae
ducebatque diem, Danaique obsessa tenebant
limina portarum, nec spes opis ulla dabatur.
cessi et sublato montis genitore petiui.だが、彼らは心の用意も資材の準備も整い、至る所から参集していた。
わたしが海を越えてどの土地に連れていこうと、同行する覚悟であった。
いまや、イーダ山の頂上から暁の明星が姿を見せ、
朝の太陽を連れてきていた。ダナイ人たちは門という門の
入り口を固めている。誰かに救いを求める希望はいっさいなかった。
わたしはこの場を離れ、父を背負って山の奥へと歩き始めた」。
サウス・カロライナ州のモットーに関して
イギリスを脱出し、新天地に新しい祖国を築いた自分たちを『アエネーイス』の主人公一行と重ね合わせるため、表題のフレーズを州のモットーに採用したのかもしれない、と想像をめぐらせます。

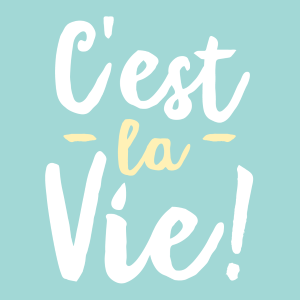
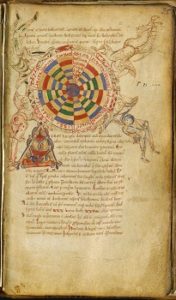
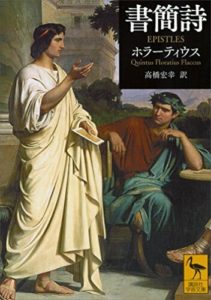
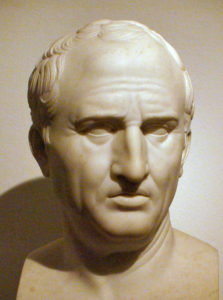
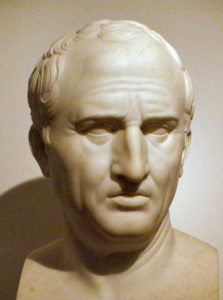
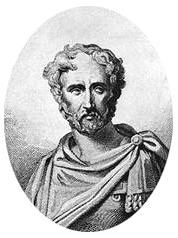
コメント