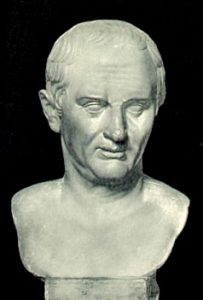ヘーローとレアンドロスの悲劇について、ウェルギリウスは『農耕詩』第3巻258-263で次のように言及しています。
「恐ろしい愛に身を焦がす、かの若者を想え。彼は真暗な夜更けに、嵐が吹き荒れ波立ち騒ぐ海峡を泳ぎ渡る。彼の頭上には天の巨大な門が雷鳴を発し、断崖に突き当たる波は引き返せと叫ぶが、哀れな両親も、まもなく嘆きのあまり死ぬことになる乙女も、彼を呼びとめることはできない。」(河津千代訳)
このエピソードは「人間にも動物にも愛は変わりなく襲いかかる」という考え (amor omnibus idem) を裏付ける具体例として語られています。
一方、詩人は先行する箇所で、「愛を遠ざける必要性」を強調しています。いわく、「家畜を愛や盲目の愛の刺激から遠ざけることほど、その体力を強める上で効果的な世話はない。」と。
この言い回しは、エピクロス派の詩人ルクレーティウスの表現(4.1052以下)をふまえています。
・・・従ってこのように愛の神の矢に打たれた者は――女らしい体つきの少年がその矢を放つにせよ、女が体全体から愛の魅力を放つにせよ――矢を放った者と交わって、己の体から溢れる液体を相手の体に注入せんと努めるものである。なぜなら無言の欲望(cupido)が来るべき快楽を予感させるからである。これが我々の愛(Venus)であり、ここから愛の名称も生まれてくる。また、ここから愛のあの甘い滴が心の中に滴り落ち、けだるい苦悩が後に続く。例えば、愛する相手が目の前にいない時でさえ、その面影は眼前にあり、相手の名前が耳元で甘美に響くことがあるが、そのような面影は断じて退けるべきであるし、欲望に火をつけるようなものは何であれ、遠ざけなければならない。心を他に転じ、体内に集まった液体はどのような肉体にでも放出するがよい。いったん一人の相手に惚れ込んだ場合でも、懊悩や頑固な苦しみを胸の内にとどめたりしてはならない。初めの傷を新しい刺激によってかき乱し、その傷がまだ新しいうちに、移り気な愛にわざと翻弄されながら、その治療に当たったり、心を他に転ずることができなければ、恋の傷はやがて大きく成長し、心中に温存することで慢性化する。日毎に狂気がつのり、苦悩もついには深刻なものとなる。
ウェルギリウスの場合、たしかに家畜の世話と関連づけて「愛は遠ざけよ」と述べていますが、初めに触れたヘーローとレアンドロスの例でもおわかりいただけるように、そうすることがむしろ不可能な現実を──第4巻エピローグの「オルペウスとエウリュディケの物語」とともに──強調しているように思われます。この点がルクレーティウスとの相違点です。
物の本質について (岩波文庫 青 605-1)
ルクレーティウス 樋口 勝彦