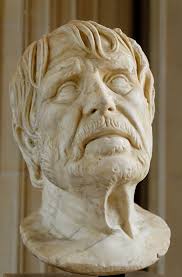ウェルギリウスの『農耕詩』第4巻エピローグの試訳
ウェルギリウスの『農耕詩』第4巻の後半には「アリスタエウス物語」と呼ばれる「脱線話」(digression)があります。その中に次に紹介するような「オルペウスとエウリュディケ」のエピソードが見いだせます。以下は試訳です。
453
「ある神の怒りがおまえを苦しめている。おまえは大きな罪をおかし、今その罰をこうむっている。この罰をおまえに与えるのは、不幸なオルペウス。彼の悲しみは決して自分のせいで生じたのではない。彼は奪われた妻(エウリュディケ)のことで激しく怒り、運命が干渉しないかぎり、おまえにこの罰をくだすのだ。
457
実は、彼女は、おまえから逃れようと川沿いをまっしぐらに走っていた。そして、大蛇が足下の深い草むらの中にいて、川岸を守っているのに気づかず、命を落とした。このとき、森のニンフの仲間たちは、山の頂を号泣で満たした。ロドペの丘も、高いパンガエアの山並みも、レスス王の戦いの土地(トラキア)も、ゲタエ人もヘブルス川も、アテナエのオリテュイアも、みんな涙を流した。
464
オルペウスは、うつろなキタラを奏で、切ない愛をなぐさめるため、愛しい妻よ、おまえを歌った。孤独な岸辺で、昼夜を問わずおまえのことを歌い続けた。彼はタエナルス山の峡谷、すなわちディス(冥界)に続く深い入り口、さらに、黒い恐怖の漂う陰惨な森、これらの中に分け入り、死霊と恐るべき冥界の王、そして人間の祈りによっても決して穏やかな心をもたない者たちに近づいていった。
471
すると、彼の歌によって動かされた影たち、実体をもたず、光を欠いた亡霊たちが、暗黒の世界の奥底から集まってきた。さながら、宵の明星や、冬の雨が山から駆り立てるとき、葉かげに身を隠す千の鳥のように。彼らは、母や男たち、英雄たちの命なき肉体、少年たち、未婚の娘たち、両親の目の前で、火葬薪に置かれた若者たちであった。その周りには、黒い泥や醜いコキュトス川の芦、ゆっくりした流れを伴なった陰気な沼が彼らを取り囲んでいた。さらに九重に流れるステュクス川がその内側に閉じ込めていた。
481
実に冥界の館そのものが、彼の歌には言葉を失った。黄泉の国の最奥部にある奈落の底も、青黒い蛇を髪に巻き付けた復讐の女神たちも感嘆した。ケルベルス(冥界の番犬)は三つの口を開けて立ちつくし、風がやみ、イクシオンの車輪は停止した。
485
今やオルペウスは踵をかえし、あらゆる苦難を乗り越えていた。連れ戻したエウリュディケは、背後からオルペウスにつき従い、上方の空気を目指して進んでいた。(というのは、この約束をプロセルピナは与えていたからだ)。だがこのとき、突然の錯乱が、不用意な恋人(オルぺウス)の心をとらえた。それは許されるべき錯乱だった。もしも、冥界の神々が許すすべを心得ていたならば。
490
彼は立ち止まった。そして、今まさに光の下に姿を現そうとした妻エウリュディケを、理性を失ったオルペウスは、(約束を)忘れ、ああ、振り返って見てしまったのだ。このときすべての苦労は水の泡となった。残酷な専制君主の掟は破られて、三度アウェルヌスの湖で、雷鳴がとどろいた。
493
エウリュディケは言った。「何という錯乱が、哀れな私とあなたを破滅させたのか、オルペウスよ。ああ、ふたたび、残酷な運命が私をうしろに呼び戻し、眠りが、泳ぐまなこを閉じていく。もう、さようなら。私は大きな夜の闇に包まれて、運ばれていく。力ないこの手のひらをあなたに差し出しながら、ああ、もうあなたのものではない、この私は。」
499
こういい終えると、彼女はたちまちオルペウスの眼から、ちょうど煙が微細な空気の中に混じるように、四方八方に消えていった。オルペウスはむなしく影をつかもうとしたが、これ以上多くの言葉を語ろうとする彼を、彼女は二度と見ることはなかった。冥界の渡し守(カロン)は、オルペウスが再び目の前の川を渡ることを許可しなかった。彼はどうすればよかったのだ。二度も妻を奪われて、彼はどこにいけばよかったのだ。どんな涙によって、亡霊たちを、いかなる神の力を、自らの祈りによって動かせばよかったのか。
506
エウリュディケはこのとき、冷たい体となって、小船でステュクス河を渡っていた。人は言う、オルペウスはまる7カ月の間、休みなく、荒涼としたストリュモン川のそばの高い崖の下で涙にくれ、冷たい星空の下で、己の不幸を歌ったと。虎の心を和らげ、歌によって自らの悲しみを語りながら。さながら、ポプラの葉かげで、ピロメラ(ナイチンゲール)が、悲しみのあまり、失った子供たちを嘆くように。それは残忍な農夫が、羽根のはえ揃っていない子供の鳥たちを、目ざとく見つけ、巣から追い出したときのこと。母鳥は夜通し泣き通し、枝に座って悲しみの歌を繰り返しながら、あたりを悲しみの叫びで満たす。
516
いかなる愛も、いかなる結婚の誘いも、彼の心を動かさなかった。彼は一人で、北の氷、雪降るタナイス川、年中リパエイ山の霜で覆われた大地を渡り歩いた。奪われたエウリュディケのこと、果たせなかった冥界の王との約束を嘆きながら。キコネスの女たちは、これほどまで妻を思慕するオルペウスに侮辱を覚え、バックスの夜の祭りと神々への犠牲を行う間、この若者(オルペウス)の体を引き裂き、大地に広くまき散らした。
523
このとき、父なるヘブルス川は、白い首から切り離されたオルペウスの頭を、流れの中ほどで転がすように運んでいった。オルペウスの魂は体から離れたが、声はひとりでにエウリュディケと叫んでいた。冷たくなった舌が、「ああ、あわれなエウリュディケよ!」と呼ぶと、川岸はいっせいにエウリュディケとこだました。