Cultura animi philosophia est. 哲学とは精神を耕すこと
キケローの『トゥスクルム荘対談集』2.13 に見られる言葉です。 文頭の Cultura は英語の culture の語源です。cultus は「耕す」という意味の動詞 colo からできた名詞で、「耕作、耕すこと」が原義です。二つ目の animi は「心、精神」を意味する animus の変化形です。cultus とあわせ、「心を耕すこと」と訳せます。三つ目の philosophia は英語の philosophy の語源です。もとをただすと、ギリシア語Φιλοσοφία に由来します。ギリシア語のもとの意味は、「知を愛すること」となります。
日本語で「哲学」という語彙は独特の語感を持っています。日頃、幼稚園児と接している者として、子どもたちは日々「心を耕している」と表現することに違和感は感じませんが、それが「哲学」かといわれたら、ちょっと言葉が大げさだと思います。「哲学」という日本語にとらわれるとそうなのですが、表題に上げたラテン語(ギリシア語)の元の意味、すなわち「知を愛すること」につながっているかと聞かれたら、答えはもちろんイエスです。子どもたちは探求心が旺盛で、いつも好奇心に輝いています。
「哲学」は明治になって philosophy の訳語として生まれた言葉です。まだまだ生硬に聞こえるのはやむを得ません。わたしたちはこの言葉が社会の中で熟成するのを待つ一方、言葉の源になった英語のフィロソフィーだけでなく、そのルーツとなるギリシア精神に遡る必要があるわけです。ちょっとした探究心、まさしく philosophia の心をもって。
関連図書:
キケロー選集〈12〉哲学(5)
キケロー 木村 健治 


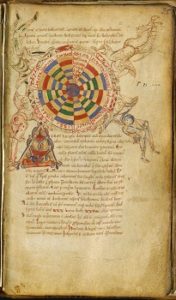


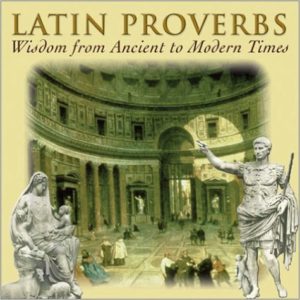


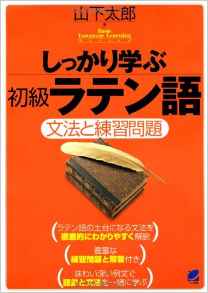
コメント