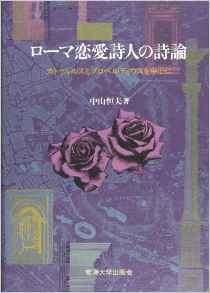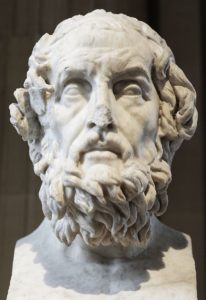1.生涯
概説
コルネリウス・ネポスの生涯についてあまり詳しいことは知られていない。大プリニウスによれば「パドゥス川(現ポー川)のほとりに住む人」と言われ(『博物誌』3.127)、北イタリアのティキヌム(現在のパヴィア)あたりの出身と推定されている。生涯の大部分をローマで過ごしたものの政治には参加せず、もっぱら文筆業に勤しんだ模様である。作家として多産ではあったが、現在では『英雄伝』として知られる本書(原題は『著名な人物について』)とごく僅かの断片が伝えられるのみで、その他の作品はすべて失われている(失われた作品については後述)。
ネポスは内乱の渦中において、キケロと手紙を交換したり(スエトニウス『ローマ皇帝伝』「カエサル」55)、アッティクスと深交を結んだが、一方では詩人カトゥッルスとも親しく付き合ったようである。ウァッロやホルテンシウスとの交際も推測されているが、文献的にそれを裏付ける資料は何も残されていない。生誕と死の年代についても定説はなく、アッティクス(前110-32)と同世代であったこと、彼の死より後まで生きたこと(ネポス『英雄伝』「アッティクス」19)などから判断して前100年頃から25年頃まで生存したと推定される。
交遊関係
ネポスの交遊関係については、次の二点を補足しておきたい。
(一)キケロとの関係
ネポスはアッティクスの別荘に招かれ、そこでキケロやホルテンシウス、ウァッロらとともにローマの歴史について議論を交わしたらしい。『英雄伝』において、ネポスはキケロによるアッティクス宛ての書簡集に言及し、「これを読む者は、この時代の通史を新たに必要としないだろう。」(「アッティクス」16)と述べ、歴史家としてのキケロの才能を高く評価している。また断片として伝わる『ラテン歴史家伝』のキケロへの賛辞では、「キケロは歴史をふさわしい言葉で語ることができた、或いは語るはずの唯一の人だったのである。…彼の死で痛手を被ったのは国家なのか、それとも歴史なのかと、私は疑問に思っている。」とも述べている。この断片の言葉遣いは、細かな点でキケロの『法律論』冒頭のアッティクスの科白(1.2) -そこではキケロが歴史を扱えばローマ人はこの部門でもギリシア人にひけをとらなくなるとの期待が述べられる -と類似している点が指摘される(1) 。この時、ネポスはキケロによる自画自賛の言葉をほとんどそのまま再録したことになる。
一方、同じく断片として伝わるキケロ宛ての書簡には次のような哲学者批判が見出せるが、これがキケロに対する痛烈な皮肉であるとみなす考えがある(2) 。
私は、哲学が人生の教師だとか、幸福な人生を完成させるものだ、などと考えるどころか、哲学論議に携わる大部分の人々ほど人生の教師を必要とする者はないと思う。事実、私が見るところ、学校で廉恥心や自制心について極めて巧みに指導している当の人々の大部分が、あらゆる欲望を求めながら生きているのだ。
このように、キケロとネポスの関係が冷ややかなものであったと推測する立場は、キケロのアッティクス宛ての書簡に見られる次の言葉を重視する。
…ネポスは果たして私の書物を望んでいるのだろうか。彼は私が自負する作品を読むに値しないと考えているというのに。『アッティクス宛ての手紙』16.5.5
資料の過少は両者の関係をめぐって様々な憶測を許すが、先のキケロ宛ての手紙に関して言えば、ネポスは哲学を否定する者では決してなく、彼にとり哲学は外見の装飾でなく実生活に活用すべきものであった(「アッティクス」17)。この手紙でも、恐らく同じ趣旨のことを述べようとしたに違いない。やはりネポスはキケロと深交を結び、その業績を高く評価していたと見るのが適切なようである。またそれゆえにこそ -ゲッリウスの伝えるように(『アッティカの夜』15.28.2) -その詳しい伝記も残したものと思われる。
(二)カトゥッルスとの関係
カトゥッルスは詩集『カルミナ』をネポスに捧げ、その献辞(第一歌)において次のように歌っている。
私はだれにこの魅力的で新鮮な小詩集を献呈しようか。
たった今乾いた軽石でよく磨き上げたこの詩集を。
コルネリウス、君にあげよう。なぜなら君は
私の下らない詩作にも何か価値があると前から考えてくれていたからね。
イタリアでただ一人、
博識で苦心に満ちた三巻の書物によって
すべての時代を説き明かそうと試みたその頃から。 (1-7)
ここで言及される「三巻の書物」とは現存しない『クロニカ(年代記)』を指すと考えられている。詩中のコルネリウスとは無論ネポスのことである。カトゥッルスは、歴史家としてのネポスの功績を評価する一方、彼が詩に対して少なからぬ関心を抱いていた事実を示唆している。またネポスはこれまでカトゥッルスの詩作を暖かく見守り、励ましてきたことも窺える。
しかし一方において、この詩行を通してカトゥッルスは皮肉を述べているとみなす意見も存在する(3) 。つまり「小詩集」、「下らない詩作」という表現は謙譲の意味で受け取る必要はなく、「よく磨き上げたこの詩集」という言葉とともに「新詩人」の創作理念を反映する(4) 。この時、ジャンルの違いはあるけれども、「博識で苦心に満ちた三巻の書物によってすべての時代を説き明かそうと試みた」ネポスの姿勢は、この理念に真っ向から対立するものとなる。すなわちカトゥッルスは、本音ではネポスの著作を無価値なものと貶めていることになる。
だが、ネポス自身「小さい詩」への共感を示唆する記述を残している(例えば「アッティクス」18参照。)。また『英雄伝』のいくつかの章は極めて短い記述で終わっているが、ここにアレクサンドリアの文学理論の反映を指摘する説もある(5) 。無論、ネポスによる「新詩人」評価については何一つ断定的なことは言えないだろう。しかし少なくともカトゥッルスにとり、ネポスは実名を挙げて自らの詩集を献呈すべき相手であった。この詩人は自分より年長の -しかも同郷の -ネポスに対し、ある種の敬愛の情を抱いていたと見るのが自然な解釈であろう。
2.失われた作品
他の作家や詩人たちの言及に基づいて、これまで次に挙げる作品の存在が推測されている。
(一)『年代記』(Chronica) -世界史の概略を語ったもので、アッティクスの『年代記』(Liber Annalis)に先行する。すでに紹介したように、カトゥッルスは詩集『カルミナ』の献辞において「(ネポスは)博識で苦心に満ちた三巻の書物によってすべての時代を説き明かそうと試みた」(1.5-7)と歌っている。この言及を根拠とし、ネポスの『年代記』は前五十四年頃(カトゥッルスの没年)には完成していたとみなされる。一方ゲッリウスは、『年代記』という書名を挙げて、ホメロスの生存がローマ建国より百六十年早かったとするネポスの説を紹介している(『アッティカの夜』17.21.3)。単なる歴史的事件のみならず、文学史に関する記述も少なからず含まれていたのかもしれない。
(二)『範例集』(Exempla) -古来より伝わる著名人の言行、逸話を集めたもので、弁論家に引用句や着想を提供する目的で書かれたと推測される。この書名は(一)と同様にゲッリウスの言及に由来する(6.18.11)。そこでは「…コルネリウス・ネポスは『範例集』第五巻において…」と述べられることから、この書物が全体で五巻以上から成り立っていたことが窺える。またスエトニウスによれば、ネポスはムティナの戦い(前四三年)におけるアウグストゥスの飲酒の習慣に触れているが(『ローマ皇帝伝』「アウグストゥス」77)、これは『範例集』における記述と解されている(6) 。そのため成立の年代は前四三年以降のこととみなされている。
(三)『カト伝』 -この書については、ネポス自身が「…この人物(カト)の生涯と人となりについては、ティトゥス・ポンポニウス・アッティクスの求めで別に出した本の中でもっと詳しく追及している。それゆえカトに興味を持った方はそちらの方を是非御覧いただきたい。」(『英雄伝』「カト」3)と紹介している。
(四)『キケロ伝』 -キケロの詳しい生涯の記述で、その死後刊行されたらしい。これもゲッリウスに書名に関する言及がある(『アッティカの夜』15.28.2)。
(五)地理誌 -大プリニウスはネポスが地理誌を書いた事実を示唆しているが(『博物誌』5.4)、内容的には必ずしも水準の高いものではなかったらしい。
(六)詩作 -詩人カトゥッルスとの交遊はネポスが詩作を試みた可能性を暗示する。従来小プリニウスの書簡の一つ(5.3)が、これを裏付ける根拠として指摘される(7) 。以下その内容を簡単に紹介しておく。
この手紙の冒頭において、プリニウスは自らの詩作-versiculus(小さい詩)という言葉を用いている-をめぐって批判的な評価が存在すること、中には彼が詩作を行うこと自体を咎める者のいることを伝えている(5.3.1)。これに対しプリニウスは次のように言う。
確かに、時には真面目でない詩を書くこともあるし、喜劇や道化芝居、叙情詩、ソタデス風の詩を楽しむこともある。(5.3.2)。だが、こういった作品は、従来極めて高い教養を持ち、思慮深く、神々しい人間たちでさえ書いてきたのだ。この事実を知らない連中に限って私が同じようなものを書いていることに驚愕する(5.3.3)。一方、私がどれほど偉大な、そしてどれほど数多くの作家を模範にしているかを知る人は、私がこれらの人物と一緒になって「過ちを犯すこと」(errare)を認めてもくれよう(5.3.4)。その中にはポッリオ、マルクス・ブルトゥス、ウァッロ、メンミウスやセネカといった面々、さらに私人の例では不十分だと言うなら、ユリウス・カエサル、アウグストゥス、ネルウァ、ティベリウス・カエサルといった皇帝の名を挙げることができる(5.3.5)。
プリニウスは、続けて「だがネロ帝の名を挙げることは控えよう」と述べた後、ネロと対比すべき「善き人たち(boni)(8) 」の例を持ち出し、「これらの中には取り分けてプブリウス・ウェルギリウスとコルネリウス・ネポス、以前ではアッキウスとエンニウスの名を数えなければならない」と述べている(5.3.6)。
右に引用した箇所において、プリニウスは自らが「小さい詩」(versiculus)を書いた事実を告げるとともに、その行為を正当化している。無論、文学史で言及するに足る内容の詩を残したと述べているわけでは決してない。一方、自分と共に「過ちを犯す人々」-この中にネポスも含まれる-についても同様のことが言えるだろう。すなわち、この書簡の記述から、ネポスも戯れに詩を書いた事実が推測できるのである。
3.『英雄伝』について
成立
ネポスは様々なジャンルから選び抜いた偉人たちの生涯を『著名な人物について』(Deuiris illustribus、前三五/四年)と呼ばれる伝記にまとめ上げた。この一部が現在でも残っており、ネポスの『英雄伝』の名で親しまれている。各分野は二巻ずつに収められ、はじめの巻で外国人が、後の巻でローマ人が扱われている。少なくとも十六巻(一説には十八巻(8) にわたって書かれたことが伝えられるので、八つ以上のジャンルから偉人たちが選び出された計算になる。確実視されているのが、(1)将軍、(2)歴史家、(3)王、(4)詩人の巻の存在であり、一方(5)哲学者、(6)弁論家、(7)政治家、(8)文法学者の巻の存在も推定されている。このうち、『英雄伝』として伝えられる内容は、「外国のすぐれた将軍たちについて」の巻全体と、「ローマの歴史家について」のうちカトーとアッティクスの伝記、その他のいくつかの断片に限られる。『著名な人物について』の第二版が出版された際(前三二年以降)、ギリシア人以外の外国人(ダタメス、ハンニバル、ハミルカル)の章が付け加えられたようであり、「アッティクス」の章も加筆と修正が加えられた(「アッティクス」19)。
ローマ人と外国人(大部分はギリシア人)を比較して著名人の伝記を紹介する手法は、ウァッロの『ヘブドマデスまたは七百人の肖像』(前三九年)にヒントを得たものであろう(9) 。ウァッロは七百人に上る人物の生涯を十六巻に収めたが、ネポスは約四百人の生涯を取り扱ったと推定されている。ただしウァッロの場合、一人物に費やされた言葉の数は極めて限定されていて、各々の肖像画の下に数行の詩を添えて人物紹介を行ったようである。この手法はアッティクスも取り入れており、それについてネポスは次のように述べている。
…(アッティクスは)実際、名声や偉業の大きさで他のローマ国民を圧倒した面々を 詩に歌い上げたが、この時各々の肖像画の下に、彼らの業績と官職の内容をせいぜい四、五行で描き出したのである。これほど重要な出来事がこれほど簡潔に語られるのはほとんど信じ難いことである(「アッティクス」19)。
すなわち、ウァッロやアッティクスは、いわばイラスト入りの短い詩行によって偉人たちの業績を歌い上げたのに対し、ネポスは散文によって著名人の活躍ぶりを描き出した点で、現存するローマ最古の伝記-『英雄伝』-を残したと言われるのである。
作品の特色
(一)ジャンルの問題
『英雄伝』は歴史書というよりも伝記文学の系譜に属する。この点については「ペロピダス」の冒頭で、ネポスが次のように述べていることからも窺える。
テバエ人ペロピダスは一般の人々よりも歴史家によく知られている。この人物の美徳についてどのように語ればよいのだろう。もしその業績について詳しく説き始めるならば、伝記というよりも歴史を記述しているのではないか、そのように受け取られることを私は恐れるのである。一方単にその概略に触れるだけなら、ギリシア的教養に明るくない人は、この人物がいかに偉大であったかがあまり明らかにならないように思われる。それゆえできる限りこの二つの困難に対処していきたい。読者の退屈と知識不足の両面に考慮を払いたいと思う。「ペロピダス」1
歴史的事実を詳しく叙述することはできる、だがこの書物においてはそれをしない、という断りは『英雄伝』においてしばしば見出されるモチーフである。例えばティモテウスに関する記述では、次のように述べる。
私はティモテウスの慎み深く賢明な人生について多くの証拠を挙げることができるのだ が、ここでは次の一例を指摘するにとどめたい。この話から、彼が仲間にとっていかに 愛すべき人物であったかを容易に推しはかることができるからである。「ティモテウス」4
同じ趣旨の言葉は、エパミノンダスの章にも見出せる。
以上はエパミノンダスの高潔さを物語る十分の証拠となるだろう。実際私はもっと多くの事実を述べることもできようが、数多くの卓越した人物の生涯をこの一巻に収めるつもりなので、今はこれだけで我慢することにしよう。「エパミノンダス」4
だが、ネポスは自分の書くものが歴史でないから簡単な記述で済ますことが許される、と考えているわけではない。今挙げた「エパミノンダス」の冒頭では、「私はエパミノンダスの人となりや生活の全体像を描こうと思うので、それを明らかにするのに役立つものは何であれ記述から排除すべきではないと考える。」と述べ、全体の構成については、「まずエパミノンダスの家系について、次いでどのような教育を誰から受けたのかについて、次にその性格や天与の才能について述べてみたい。多くの歴史家によって精神の美徳以上に評価される軍事面での業績については最後に触れたいと思う。」と語っている。先にネポスは、ペロピダスの「業績」を詳しく説くなら「伝記」ではなく「歴史」を描いていると受けとられかねないことを懸念していたが、ここでもエパミノンダスの個々の「業績」ではなく、むしろその「生活」の全体像を描くことを主題として挙げている。ネポスの描こうと努める「伝記」(vita)とは、偉大な人物の賞賛に値する「人生」(vita)に他ならない。偉人を偉人たらしめる精神的卓越性、すなわちティモテウスの慎み深さやエパミノンダスの高潔さなどを十分物語ることができる限り、必ずしも史実を事細かく記述していく必要はない、というのがネポスが本書において一貫して下す判断である。従来、いくつかの資料的欠陥(10)に加え、情報量の乏しさも、本書を本格的な歴史書とみなせない理由の一つに数えられてきた。だが、不正確な記述はともかくとして、情報量の多少については今見た伝記作家としてのネポスの判断が働いていると見るべきであろう。
(二)内容の特色
『英雄伝』には、基本的に次のような特徴が認められる。
(イ)主人公の性格を照らし出すエピソードが紹介され、倫理的教訓が導かれる。
(ロ)紹介する人物が徹底して賞賛される。
(イ)はペリパトス派の伝記文学の特徴を示し、(ロ)は賞賛文の伝統を反映すると言われる(11)。ペリパトス派は、人間の多様な精神の在り方に関心を抱き、歴史的因果関係よりも、個々の人物の性格描写に主眼を置いた伝記文学を発達させた。一方、古来ギリシアでは葬送歌や祝勝歌等において、故人や勝利者を賞賛する伝統があったが、弁論術の発達とともに、ある人物の美点を賞賛する訓練 -政治や裁判において重要な意義があったらしい -が行われるようになった。
人物を徹底して賞賛する立場は、性格を客観的に描写する立場と矛盾する。プルタルコスに比べれば、ネポスの人物描写には一定の取捨選択が行われていることが窺える。だが『英雄伝』は、単なる賞賛文と片付けてよいほど平凡で単調な作品ではない。今回訳出した二十五の人物の描写は、基本的には賞賛文の系譜に属することを印象づけながらも(12)、一方ではペリパトス派の手法が取り入れられることで、叙述に陰影と奥行きが与えられている。例えば「コノン」の章では、その生涯を賞賛に値するものとして描写する一方、「だが結局、コノンも他の人間と同様、逆境より順境において思慮が足りなかった」と述べて、その破滅への過程を紹介する。コノンはイオニアとアエオリアをアテナエ人の手に取り戻そうと画策したが、この計画が発覚し幽閉されたのである。しかしネポスは、コノンが実力以上の野望を抱いたことは認めながらも、それが道に背くものではなく、むしろ是認されるべきものであったと述べている。なぜなら、彼はペルシア王の力よりも祖国の力の増大を図ったからである。ネポスは、主人公の欠点-思慮が足りないこと-を述べるかに見えて、実際にはその美点-愛国心-を強調している点で、賞賛文の基本姿勢は崩していない。
ペリパトス派の人物描写の特徴-美徳と悪徳の公平な紹介-を最も色濃く反映する箇所としては「アルキビアデス」の章が挙げられる。冒頭でネポスは、「悪徳でも美徳でも彼をしのぐ者はなかったというのが定説となっている」と述べ、「一人の人間にこれほど矛盾した相反する性格があることに誰もが驚く」と言う。ヘルメス柱像を倒した首謀者としてアルキビアデスが疑われたのも、彼が「一個人であるにはあまりにも勢力も能力もありすぎるとみなされていたから」と説明し、「(アルキビアデスは)大いに害にもなり得るし役にも立ち得るという理由から、人々は彼に多大な期待のみならず、大変な懸念をも抱いていた」と付け加えている。また、パウサニアスに関しても、冒頭で「偉大な人物であったが、人生のあらゆる面で気まぐれであった。美点が光彩を放つ一方で、汚点にまみれていたのである。」と述べている。彼は勝利に驕り、数々の混乱を引き起こし、さらなる野望を抱いた結果、「戦争での大いなる栄光を見苦しい死によって汚した」のであった。
だが、主人公の悪徳が直接言及されるのは、『英雄伝』においては、むしろ希なケースと言える。ネポスは、偉人の性格の欠点を指摘する代わりに、その不運に言及することがしばしばある。特に目立つのが、主人公が国民の妬みを買って断罪されるというモチーフである。これは賞賛文の手法とは一見相容れないが、実際には主人公の美点を強調する効果を生む。例えば、ミルティアデスが国の監獄に投じられそこで生涯を閉じたのも、その悪徳ゆえでなく、むしろ善政のためであった。ネポスによれば、ミルティアデスは暴力によらず臣民の意思によって永続的な統治権を握り、僭主と呼ばれてはいたが「正当な」僭主であった。彼はこの権力を善政によって保持したが、アテナエ人はいかなる市民にせよ権勢をふるうのを極度に恐れていたのである。「テミストクレス」、「アリスティデス」、「キモン」、「ティモテウス」の各章も、立派な指導者が国民の妬みのために断罪される例を伝えている。
一方、この「妬み」のモチーフの扱いは、章によって多様でもある。エパミノンダスは、 国民の羨望による不遇をものともせず、政敵による死刑の告訴も機知によって免れた。これに対し、エウメネスは、身に降り懸かる羨望をあらかじめ予測し、効果的な処置を講じたものの、最後には他の将軍たちの裏切りによって敵軍に引き渡された。ティモレオンは、市民の意に反してでも支配者になれるほどの力を持っていたが、恐れられるよりも愛されることを望み、支配権を放棄すると一私人として余生を過ごした。すなわち自らの思慮によって「妬み」を回避することに成功した。ネポスは、これを実に賢明な判断であったと評価する。
『英雄伝』に見られるペリパトス派の伝記文学の影響としては、あるエピソードを紹介した後、何らかの教訓を導く手法においても見出せる。ネポスはミルティアデスがわずかな戦力で十倍の数のペルシア軍を破ったと述べた後で、次のようなエピソードを伝えている。
この勝利の報酬としてどのようなものがミルティアデスに与えられたかをここで述べることは、あらゆる国の性質は同じだということを一層容易に知るためにも、あながち場違いではあるまい。というのも、ローマ国民の報償はかつてはまれでわずかであって、だからこそ栄光あるものだったのに、今ではむやみに多くてありふれているわけだが、それとちょうど同じ事情が昔のアテナエにも見られるからである。アテナエと全ギリシアを解放したとしてこのミルティアデスに授与されたのは次のような栄誉だった。すなわち、ポエキレと呼ばれる柱廊にマラトンの戦いの様子が描かれる際に、彼の肖像が十人の将軍の中で第一の位置を占め、その姿は兵士らを激励してまさに戦端を開こうとしている、というものだったのである。だがこの同じ国民が、もっと大きな権力を手に入れ、政務官の乱費によって堕落した後は、パレルムのデメトリウスのために三百もの像を決議したのである。「ミルティアデス」6
目で見える名誉の証しよりも、真に誉れある行為を賞賛すべきだという考えは、本書においてしばしば見られるものである。この考え自体が特に注目に値すると言うのではない。むしろ、ネポスが偉人にまつわる様々なエピソードを紹介しながら、同時に自らの倫理観を垣間見せる工夫を行っている点に我々は目を向けたい。この工夫自体が、ともすれば平板になりがちな賞賛文の記述にある種の抑揚をつけている。また、現実のローマ社会との比較も叙述に現実味を与えている。類例を挙げよう。アゲシラウスが国家への忠誠を何より尊んだ例に触れて次のような見解が示される。
この機におけるアゲシラウスの愛国心は武勇の徳と同様に評価されるべきものである。 アゲシラウスは勝利を収めた軍隊を率いてペルシア王国を征服する自信に溢れていたが、まるでスパルタの集会所における一私人のように、その場に居合わせてもいない政務官の命令に従順に従ったのである。まったくわが国の将軍たちもこの範例に従っていればよかったのにと悔やまれる。だが本題に戻ろう。「アゲシラウス」4
さらに「エウメネス」の章では、マケドニアの密集隊の驕漫を描写しながら、次のような意見を述べている。
そこで、今日のローマ(古参)兵もこのマケドニア兵と同様に振る舞い、その自制のなさや過度の放縦によってすべてを台無しにし、自分たちが戦う相手ばかりか味方をも滅ぼすのではないか、といった危惧がある。人はもしマケドニアの古参兵の行いを読めば、今日のローマの古参兵の行いとの共通点を見出し、両者の間には時の隔たり以外に何ら異なる点がないことがわかるだろう。では当時の出来事に話を戻すことにしよう。「エウメネス」8
以上例示してきたように、ネポスは『英雄伝』において、ただ主人公の生涯を美化して物語るだけではない。偉人を賞賛する姿勢と矛盾しない形で、あるいはその礼讃を一層引き立たせる効果を狙って、主人公の短所や悲運にも言及する。また各々の人物像を彷彿とさせるエピソードを語る中で、自身の価値判断を示唆する工夫も払っている。「序文」において明らかなように、ネポスは各々の文化の相対的価値を主張している。しかし一方では-今挙げた例からも窺えるように-現実のローマ社会を昔のギリシア社会と比較することで、いつの世にも変わらず見られる人間精神の愚鈍ぶり-名誉心や権力欲-に読者の目を向ける。
とはいえ、「ネポスの思想」を抽出し分析し得るほど、『英雄伝』が十分の教訓や示唆に満ちているわけではない。この点で、この書は他の歴史書に比べていささか物足りない読後感を与えるかもしれない。だが本書は-ネポスがそう区別していたように-歴史書としてではなく、むしろギリシア以来の伝統を踏まえた伝記文学の一つとして接していく必要があったのである。今後、古典期の伝記文学の研究が発展することにより、ネポスの独創性-いかなる工夫を凝らしてこの伝統を継承し新しい要素を盛り込んだか-が一層明らかになることを期待しつつ本解説を結びたい。
なお、本書の訳出にあたり使用したテクスト、注釈書は以下の通りである。
A.M.Guillemin, Cornelius Nepos, Bude, 1923.
H.Ebeling and E.Ortmann, Coenelius Nepos, Teubner, 1870.
N.Horsfall, Cornelius Nepos, Oxford, 1989.
K.Nipperdey-K.Witte,13th ed.,Dublin/Zurich, 1967.
R.Roebuck, Cornelius Nepos, Bristol, 1987.
J.C.Rolfe, Cornelius Nepos, Loeb, 1984.
E.O.Winstedt, Corneli Nepotis Vitae, OCT, 1971.
注
(1) E.A.Robinson,Cornelius Nepos and the Date of Cicero’s De Legibus, TAPA LXXI,1940,524-31.
(2)E.M.Jenkinson,Cornelius Nepos and the Early History of Biography at Rome,
ANRW 1.3, 704.
(3)Jenkinson, 703.
(4)カトゥッルスはアレクサンドリア派の文学理論を信奉していた。この理論においては彫琢を重ねた小さい詩の価値が尊ばれるが、キケロはこの信奉者たちのことを「新詩人たち」と呼んだ。
(5)Rolfe, xii.
(6)Rolfe, viii
(7)Rolfe, viii.
(8)boniとはいわゆる善人の意味ではなく、政治的には保守的で、ローマの伝統的価値観を重んじる人間を意味する。cf.Cic.Dom.8; Nep.Thr.2.4.
(9)Horsfall, 11.
(10)Horsfall, 11.
(11)Jenkinson, 713-14.
(12)Jenkinson, 705ff.なお伝記文学に関する全般的な説明は、A.モミリアーノ著、柳沼重剛訳『伝記文学の誕生』(東海大学出版会),1982が有益である。
(13)「リュサンデル」では徹底した批判が行われている点で、他の章と趣を異にしている。