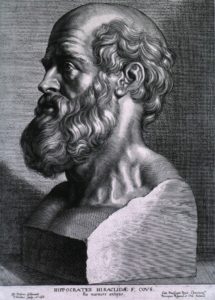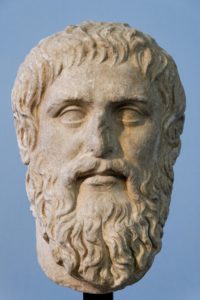現代に生きる古典語(2)
前回は英語の「スクール」という語が、ギリシア語で「暇」を意味することや、日本語の「教育」に相当する英語の「エデュケーション」の本来の意味(引き出す)などをご紹介しました。
では昔のギリシア人は「暇な」学校で何をしていたのかというと、ひとつには哲学が重視されました。哲学は英語でphiosophyといいますが、元のギリシア語ピロソピアとは「知恵を愛する」という意味です。そして知恵(ソピア)とは、暗記しうる知識とは異なり、人間が幸福に生きるための正しい判断力を意味します。
一方、立派な精神にふさわしい立派な肉体を鍛えるための体育も重視されました。体育館は英語でgymnasium、略してジムといいますね。これはラテン語のつづりをそのまま残していますが、本来はギリシア語のgymnazein(裸で鍛える)という動詞が語源です。今でいうボディビルのようなトレーニングをしていたようです。
さて、古代ギリシアの学校としては、プラトンのつくった「アカデメイア」が有名です。プラトンは自らの師ソクラテスの教えを36の対話篇に記し、後世に伝えるとともに(そのいくつかの作品は、文庫本で手に入ります)、現実社会を変革する人材育成の場としてアカデメイアを設立しました。
例えば『国家』(ポリテイア)という作品では、哲学を修めた君士がどのようにして理想国家を運営しうるのかといった問題(哲人統治の思想)を追及しています。このように、天下国家のありかたを真正面から取り上げて論ずる態度は、我々日本人にとっては堅苦しいこと、縁遠いことのように思われますが、ギリシア語の原題「ポリテイア」は、古代ギリシアにおいてはごく平凡な日常語で、「ポリス(都市国家)の住人(=ポリテース)のあり方」といった感じの意味です。司馬遼太郎氏の著作に『この国のかたち』というのがありますが、このタイトルの方がポリテイアの訳語としてふさわしい響きをもっています。
ところで、今紹介したポリテイア、ポリテース、ポリスといった語は、互いに密接に関連しながら「政治」を意味する英語politicsの語源になっています。英語圏では、政治が市民の生き方、国家のあり方と緊密に関わる問題として意識されている証左です。ついでながら、国家を表すポリスとは、警察を表すpoliceの語源でもあります。国家の治安をつかさどることと関連しているからですね。
一方、プラトンの『国家』を模倣したローマの文人にキケローがいます。『国家論』と訳される作品を残していますが、原題はラテン語でDe Re Publicaといいます。Deは英語のabout、Reはthing、Publicaはpublicに相当しますので、直訳しますと「公の物について」となります。つまり、古代ローマにおいて、「国家」とはまさしく「みんなのもの」という意味だったのです。今もrepublic(共和国)という英語の単語に、このラテン語のつづりが残されています。ついでながら、「出版する」を意味する英語publishは、今ふれたpublicと関連しています。書いたものを「公にする」というニュアンスが込められています。
さて、政治の話が出たついでに、「社会」を意味するsocietyという英語の語源を考えてみましょう。これはラテン語のsocietas(親交、友愛、絆を意味します)からできた言葉で、さらに遡れば「仲間」、「友」を表すsociusという語からできた単語です。またこのsociusという言葉自体「分かち合っている、結び付けられた」という意味をもつ形容詞でもあります。とすれば、欧米人はsocietyというつづりを見て、親しい友に感じる愛着を無意識のうちに呼び覚ますのでしょう。少なくとも我々が「社会問題」と口にしたときに「構える」気持ちとは、まったく別の語感が込められているはずです。
ラテン語sociusを語源とする英単語としては、他にassociation(協会)があります。意外なところではsoccer(サッカー)もsociusと関連しています。元はassociation footballと呼んでいたのを、短縮してsoccerと称するようになった、というのがその種明かしです。
ふたたび話をギリシアの昔に戻します。上にあげたソクラテスは、「無知の知」という言葉で有名ですが、これはどういう意味でしょうか。デルポイの神託で「ソクラテスより知恵のある人間はいない」というお告げを聞いた彼は、この神託の真実性を疑いました。そこで自分よりも知恵を多くもっていそうな人物に、人生の意味や美の問題、究極の真理に関する疑問をぶつけました。その結果わかったことは、これらの人物は単に知ったかぶりをしているだけで、自分の無知にぜんぜん気づいていないということでした。つまり、無知を自覚した自分とそうでない連中の間には、じつに大きな違いがあることに気づいたのです。すなわち、「無知の知」は「無知の無知」にまさるという点で、ソクラテスは神託が正しかったことを確認したのです。
さて、この「無知の知」との関連で、話は私たちの生きる現代—21世紀のネットワーク社会—まで一気にとびます(笑)。ネットワークをめぐる昨今の議論においては、個々の情報を正しくjudgeする能力が重要であるという意見をしばしば耳にします。この能力を英語ではwisdomとよび、ギリシア語ではソピア(知恵)とよぶのです。インターネットの普及は、このようなソピア重視の方向に拍車をかけ、本来の意味で哲学を指向する時代の流れを形成していくでしょう。
ところが、今までの日本社会では、手短にいえば、より多くの知識を持つ方法論が重要視されてきたわけです。知識を暗記することは、出世に役立つ正道であるとも信じられてきました。事実、従来の学校のテストは、その能力の有無を調べる構造になっています。しかし、冷静に考えた場合、人間は所詮、自然界について、あるいは生や死の問題について、知らないことがほとんどです。どのみち99パーセントのテーマについて、素人同然で死んでいくのでしょう。とすれば、上でふれたソクラテスの「無知の知」という考え方が、これからのネットワーク時代において、案外重要な意義をもつのではないかと思うわけです。
具体的にいえば、今までのように各人がばらばらに知識をためこみ、その情報量の多寡を競い合うよりも、自分の本当に知りたいことを明確にし、わからないことを他人から上手に聞き出す能力を身につける方が、はるかに大切な態度になってくるでしょう。わかることは喜んで他人に伝え、わからないことは他人から教えてもらうという社会の在り方こそ、ネットワーク社会の重要な特質ではないでしょうか。
今私は「社会」という言葉を使いましたが、英語のsociety(社会)とラテン語のsocius(友)の関連性については上で見たとおりです。日本人同士で「社会問題を話し合う」というと、仰々しく感じられますが、英語でsocial problemといえば、「仲間の問題、みんなの問題」くらいのニュアンスがあります。言葉の持つイメージがまるで異なりますね。
ところで、先にふれた司馬遼太郎さんは、日本語の「人」という字について、ななめの画がたがいに支え合って構成されていることに感動を覚えると書いておられます。「社会とは、人間が互いに支え合う仕組みにほかならず、人は決して孤立して生きられるようにはつくられていない」とも。日本語にせよ英語にせよ、ときには語源に遡って、あれこれ思いを巡らせるのも楽しいものです。