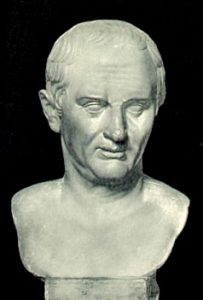エコーってご存じですね(カラオケにあらず)。手元の『ギリシア神話小事典』(バーナード・エヴスリン、小林稔訳、教養文庫)を見ますと、
「心の優しいニンフで、ゼウスがヘラの監視から逃れるのを助けた。女神のヘラはこのことを聞いて怒り、エコーが自分では口がきけないようにし、ただ話しかけた人の最後のせりふだけ繰り返すことを、彼女に許した。このためエコーは、美男で、うぬぼれ屋のナルキッソス(ナルシス)にうまく言い寄ることが出来なかった。ナルキッソスはエコーの話を退屈だと思ったのである。彼女は悲しみのあまり姿を消してしまい、今はただどこかの谷間か、丸天井のある場所にしか見当たらない。そういう場所で、呼びかけてやれば、エコーは返事をしてくれることだろう。」
と説明されています。
では、美しいエコーの恋を拒んだナルキッソスの運命は、その後どうなるのでしょうか?彼は水に映った自分の姿に恋するあまり、死んでしまうのです(これは愛を侮辱した罰とされます)。彼の死体は消え、かわりに、黄色い水仙の花が見つかったといわれます。余談ですが、英語で水仙のことを narcissusといいます。
次に引用するのは、その最後の場面で、古代ローマの詩人オウィディウスの『変身物語』第3巻(中村善也訳)の一節です。少し長くなりますが、読んでみて下さい。最後のあたりでエコーが再び登場します。
「・・・食事ヘの思いも、睡眠への配慮も、彼(ナルキッソス)をその場から引き離すことはできなかった。木陰の草原に身を投げ出して、みち足りぬ眼で、偽りの姿を見つめている。そのみずからの目によって、自身が滅び去ろうとしているのだ。わずかに身を起こして、まわりの木々に腕をさしのべながら、つぎのように語りかける。
「おお木々よ、こんなに辛い恋をした者があったろうか。おまえたちは知っていよう。たくさんの人たちに、手頃な逢い引きの場所を与えて来たのだから。おまえたちの生涯は幾世紀にもわたるというが、その長い年月のあいだに、こんなにもやつれはてた誰かをおぼえているだろうか?わたしには、恋しい若者がいて、彼を見てもいる。
だが、この目で見ている恋の相手が、いざとなると見当らないのだ。それほどまでの迷妄が、恋するこの身にとりついている。なおさら悲しいことには、わたしたちをへだてているのは、大海でもなく、遠い道のりでもなく、山でもない。門を閉ざした城壁でもないのだ。
ただ、わずかばかりの水にすぎない!あの若者も、この胸に抱かれたいと望んでいる。こちらが水に唇をさしのべるたびに、彼も仰向けになって、ロをさしのべて来るのだ。ほんとうに、今にも触れそうになるくらいだ。愛するふたりを妨げているのは、ほんのちよっとしたものなのだ。
おまえが何者であろうと、さあ、ここへ出て来るがよい!たぐいまれな美少年よ、どうしてわたしをあざむくのだ?追い求めるわたしを振り切って、どこへ去ろうというのか?わたしの姿、わたしの年齢が、おまえからにされるようなものでないことは確かだ。妖精たちも、わたしを愛してくれたのだ。やさしげなおまえの顔が、何かしら希望を与えてくれる。
おまえに腕をさしのべると、そちらからも腕をのばして来る。笑えば、笑いが返って来る。こちらが涙すれば、おまえのほうでも泣いている--それにも、しばしば気づいているのだ。うなずきにも、うなずきで答えてくれる。美しい口もとの動きから察するかぎり、言葉を返してくれてもいる。ただ、それがこちらの耳にとどかないだけだ!わかった!それはわたしだったのだ。
やっと今になって、わかった!わたし自身の姿に、もうだまされはしないぞ!みずからに恋い焦がれて、燃えていたのだ。炎をたきつけておいて、その炎をみずからが背負いこんでいる。どうしたらよいのか?求められるべきか、求めるべきか?
何を、いまさら、求めようというのか?わたしが望んでいるものは、わたしのなかにある。豊かすぎるわたしの美貌が、そのわたしに、貧しい身であるかのようにそれを求めさせた。ああ、このわたしのからだから抜け出せたなら!愛する者としては奇妙な願いだが、わたしの愛するものがわたしから離れていたら!悲しみのあまりに、もう、力は尽きて行く。
余命は、いくばくもない。うら若い身で、滅んで行くのだ。が、死も恐ろしくはない。それによって悲しみを捨てさることができるからだ。愛するあの若者には、できることなら、もっと長生きをしてほしい。だが、今は、ふたりが仲よく、同時に死を迎えるのだ」
こういって、狂乱状態で、あのいつもの映像に向きなおると、涙で水をかき乱した。水面がゆれ動いて、姿がぼやけた。それが消えようとするのを見ると、こう叫んだ。
「どこへ逃げて行くのだ?とどまってほしい!無情な少年よ、恋するこの身を捨てないでくれ!手には触れられなくても、見つめるだけでよいのだ。みじめなこの狂恋に、せめてそれだけのを!」
嘆き悲しみながら、襟もとから着物をはだけた。裸の胸を、青白い手で打ちたたく。胸は、たたかれて、ほんのりと赤く染まった。よくあるように、青いところに赤いところがまじった林檎のようだとも、あるいは、房の色ををさまざまに変えてゆく葡萄が、未熟のころ、やっと薄赤い色を帯び始めたようだとも--ともかく、そんなさまに似ていた。
ふたたび澄みわたった水の面に、それを見てとると、これ以上はもう耐えられなかった。黄色な蝋がささやかな火で、朝の霜が暖かい日ざしで、溶けて消えて行くように、恋にやせ細って、衰えて行く。見えない炎で、徐々にすりへらされて行く。もう、赤みをまじえた白い肌の色もなく、元気も、力も、これまでは魅力的だった外見も、消えた。かつてエコーに愛された肉体も、あとをとどめてはいない。
エコーは、しかし、このありさまを見たとき、怒りも記憶も消えてはいなかったにかかわらず、それでも、大そう悲しんだ。哀れな少年が「ああ!」と嘆くたびに、彼女は、こだま返しに「ああ!」とくり返した。彼が手でみずからの腕を打ちたたくと、彼女も、同じ嘆きの響きを返した。なつかしい泉をのぞきこんでいるナルキッソスの最後の言葉はこうだった。「ああ、むなしい恋の相手だった少年よ!」
すると、同じだけの言葉が、そこから返って来た。「さようなら!」というと、「さようなら!」とエコーも答えた。彼は、青草のうえにぐったりと頭を垂れた。おのれの持ち主の美しさに感嘆していたあのまなこを、死が閉ざした。下界へ迎えられてからも、彼は冥府の河にうつる自分を見つめていた。
彼の姉妹の水の精たちは、兄弟のために、髪を切って供えた。森の精たちも、嘆き悲しんだ。その喚きに、エコーが答える。すでに、火葬や、うち振られる松明や、棺が用意されていた。だが、死体が消えていた。そのかわりに、白い花びらにまわりをとりまかれた、黄色い水仙の花が見つかった。」
初め、エコーは相手の声を反復することしかできぬため、自分の思いを伝えることが出来ませんでした。これが悲劇の発端です。しかし最後の場面では、ナルキッソスが「ああ!」と嘆く声にこだましてエコーも「ああ!」と声を返します。ナルキッソスの最後の言葉「ああ、むなしい恋の相手だった少年よ!」とは、エコーの心そのままのせりふだったでしょう。エコーは、ナルキッソスが命を落とす最後の場面になって初めて、彼に本心を語ることができたというわけです。