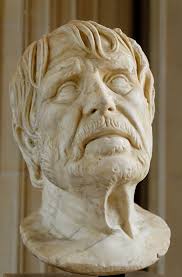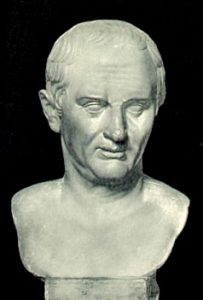『農耕詩』第2巻には、3つの「賛歌」があります(「イタリア賛歌」、「春の賛歌」、「農耕賛歌」)。
2番目の「春の讃歌」と呼ばれる箇所で、詩人は、春のにおける自然界の営みをギリシア神話(とりわけヘシオドスの『神統記』)のエピソード(「大地と天のまじわり」)を想起させながら語っています。
後半では、「思うに、当初地球が誕生したばかりの頃には、毎日がこのような日光に輝きわたり、このような光景が繰り返されていたのだろう。」とのべ、これまた『神統記』で語られる「世界の始まり」の記述を思い起こさせます。
ルクレティウスの『事物の本質について』2.991-997との関連もしばしば指摘されます。
2.315
ところで、どんなに知識のある忠告者であっても、北風によって凍てついた大地を耕すような助言なら、それを真に受けてはならない。そのころは、冬が霜によって田畑を固く閉ざし、種を蒔いても、固まった根を大地に定着させることができないから。葡萄の植え付けにとって最適の季節は、花が赤く咲き誇る春のころ。長い蛇にとっての天敵、白いこうのとりが訪れるときのことだ。あるいは秋になって急に寒くなり始めたころ。ちょうど急ぎ足の太陽神も、馬を駆ってまだ冬に到達せず、すでに夏は過ぎ去っている時分のこと。春こそは、森の木々、繁る葉にとって、もっともありがたい季節である。春には大地はふくらみ、生命を宿す種子をよび求める。
325
このとき、天なる全能の父は、豊かに雨を降らせながら、喜びに満ちた妻の膝の中に沈み、大いなる体で、妻の大いなる身体と交わって、すべての子孫を育む。道なき藪には鳥の歌声が響きわたり、家畜の群れは、定められた時期に、再び愛を求める。慈愛深き畑は、新たな生命をもたらし、西風の暖かいそよ風に、大地はその奥部を緩める。柔らかい湿り気が万物に浸透し、若草は、(春の)新しい太陽に安んじて身を委ねる。葡萄の若枝は、突然襲いかかる南風を恐れることなく、また天空で、激しい北風の襲来に駆り立てられた嵐を怖がることもなく、勢いよく若芽を押し出し、葉という葉を開いていく。336
思うに、当初地球が誕生したばかりの頃には、毎日がこのような日光に輝きわたり、このような光景が、繰り返されていたのだろう。そのときは春であった。大いなる地球には、春の日々が流れ、東風も冬の突風が吹き荒れることを控えていた。このとき、最初の獣が光を吸い込み、人間という大地の種族も、固い地面から頭をもたげ、森には野獣が、天には星座が放たれた。もしこれほどの安らぎの季節が、寒さと暑さの間になかったならば、そして、天の優しさが、大地を受け入れることがなかったならば、まだ柔らかい生き物は、この試練を克服することはできなかっただろう。